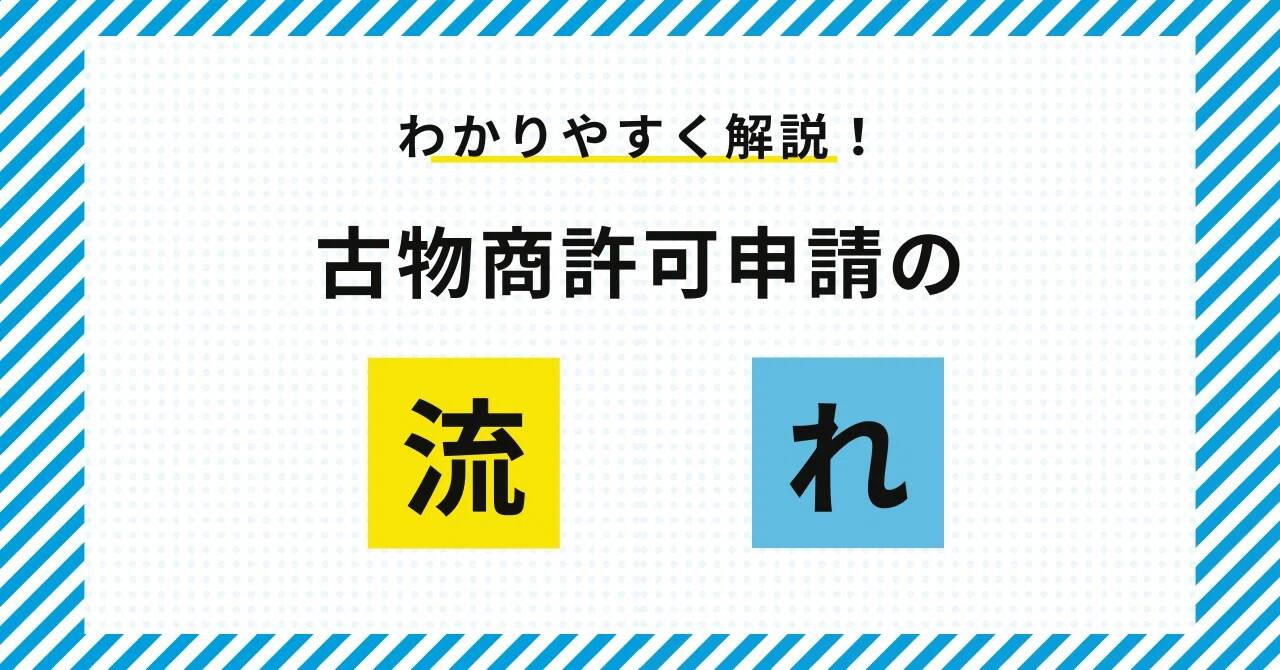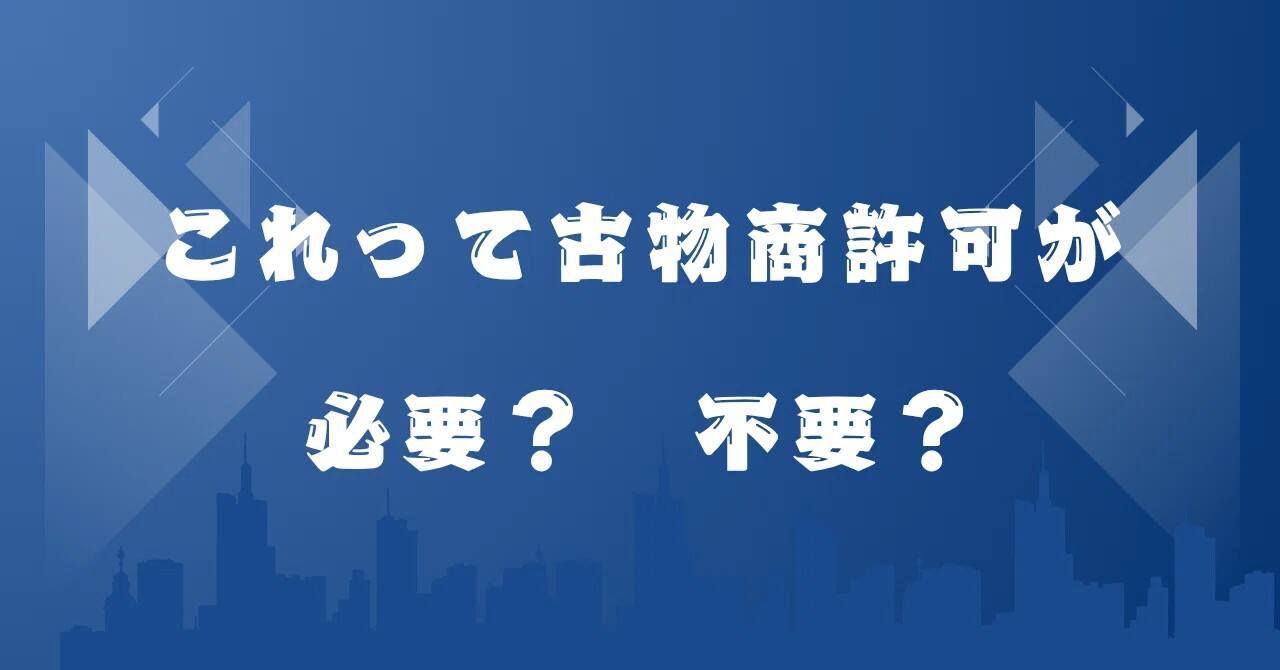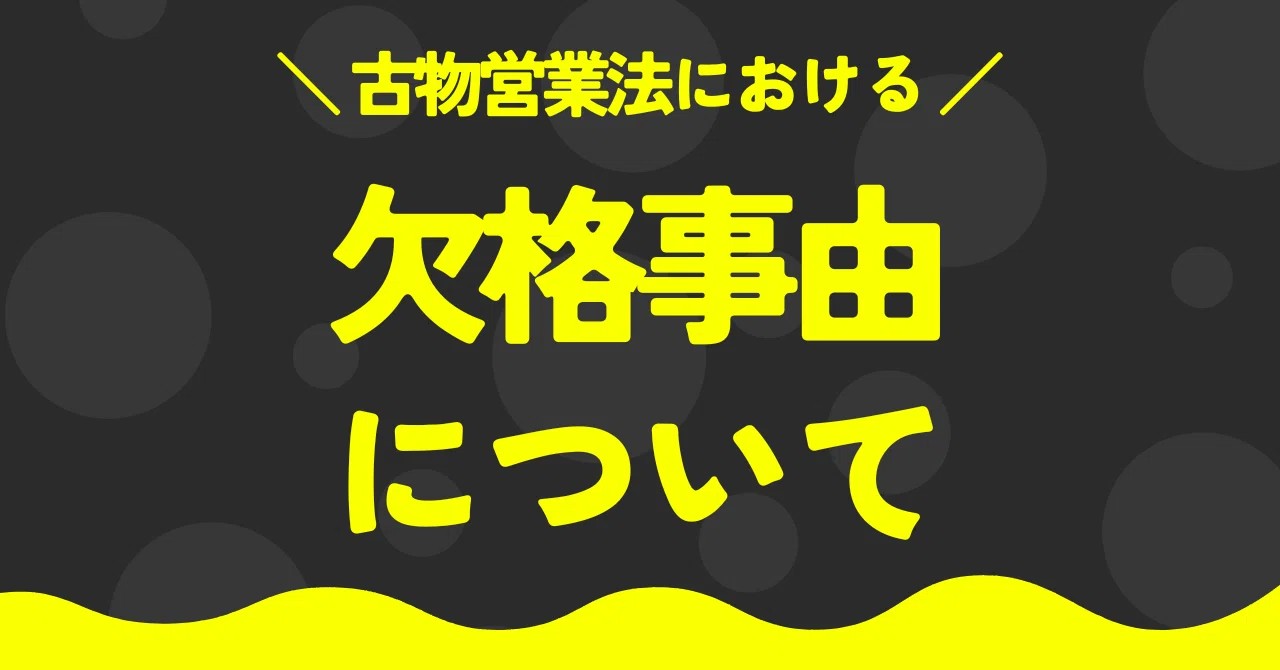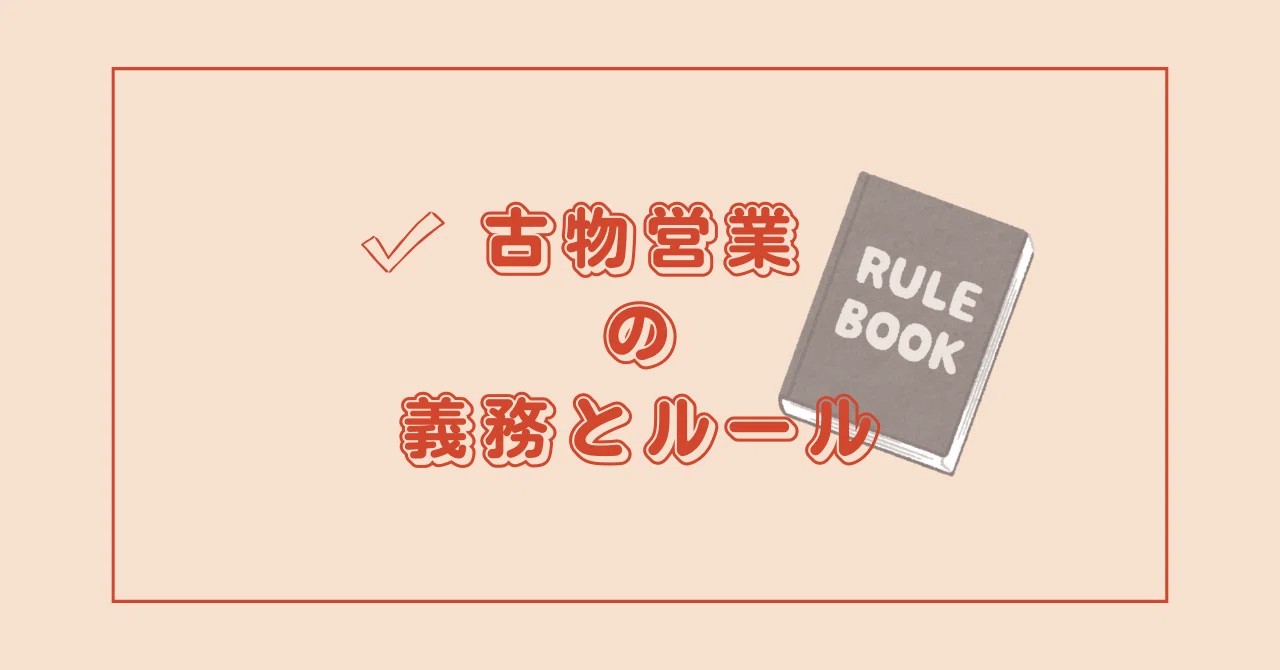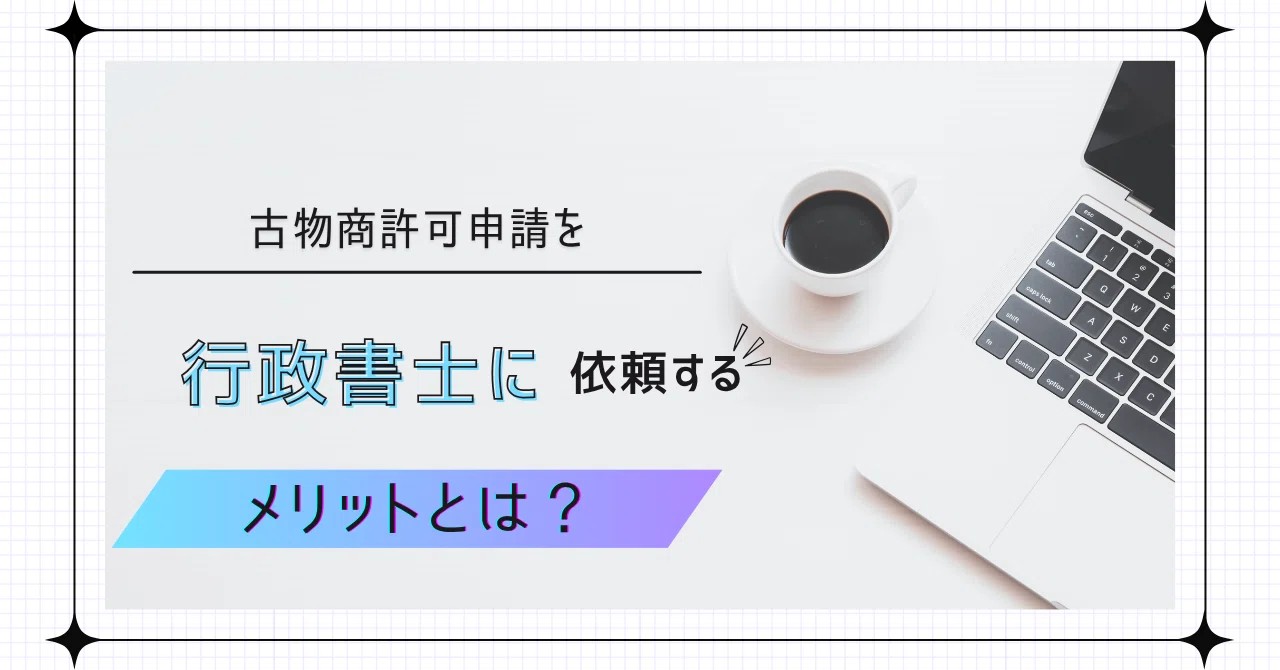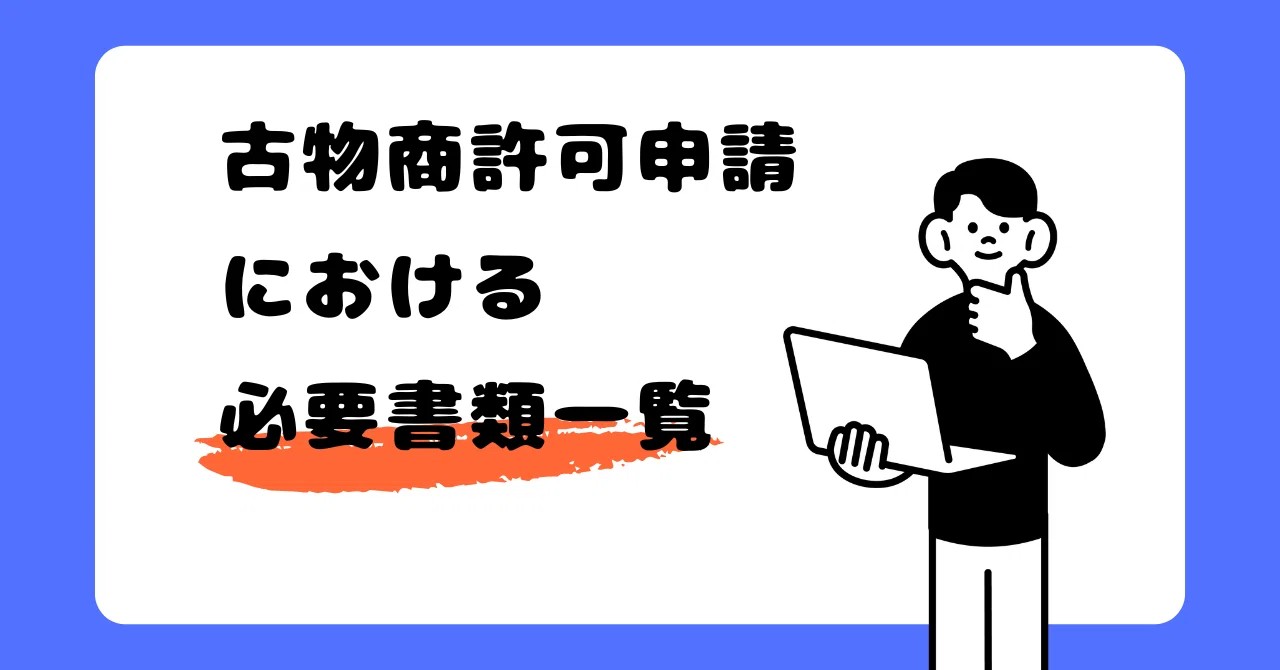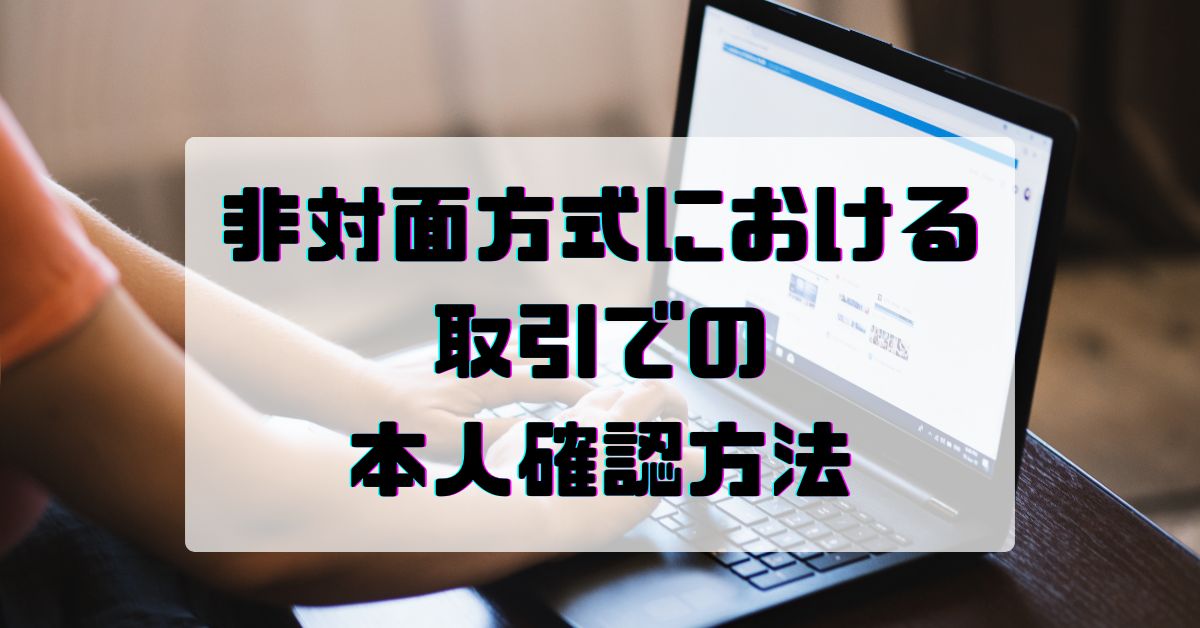行商とは

古物商許可申請の申請用紙には、『行商をしようとする者であるかどうかの別』という選択欄があります。
普段あまり耳にしない言葉ですが、今回は『行商』について解説したいと思います。
行商とは
古物商における「行商」とは、『自分の営業所以外の場所で古物の取引を行うこと』を指します。
たとえば以下のようなケースが行商に該当します。
•出張買取
•フリーマーケットやイベントへの出店
•古物市場での取引
•臨時会場(百貨店や商業施設など)での催事販売
これらのように、固定の営業所以外で古物の売買や交換を行う場合は、行商と見なされます。
そのため、古物商の許可申請をする際には、申請書の「行商を行うかどうか」の欄で【する】に〇をつけることをお勧めします。
なお、【する】に〇をつけたからといって、追加の手数料が発生することや、特別な手続きが必要になるわけではありません。
営業の制限について
「行商を行うか」の質問に対して【する】に〇をつけた場合でも、どこでも誰とでも自由に古物取引ができるわけではありません。
制限の内容は、取引相手が古物商か、そうでないかにより異なります。
| 相手が古物商 | 相手が古物商以外 | |
| 自分の営業所 | 〇 | 〇 |
| 出張買取 | 〇 | 〇 |
| フリーマーケットやイベントへの出店 | 〇 | △ |
| 古物市場での取引 | 〇 | × |
| 催事販売 | 〇 | △ |
古物商が、古物商ではない一般の方から古物を買い取る場合、その取引は原則として自らの営業所、または相手方の住所に限られます。
ただし、所轄の警察署に対して仮設店舗営業の届出を行うことで、仮設店舗(例えば催事会場やイベントスペースなど)での取引も可能になります。
「行商を行うかどうか」の欄で【しない】に〇をつけた場合
「行商しない」に〇をつけた場合、出張買取やイベント会場での販売・買取といった営業所外での取引ができなくなるため、営業活動は大きく制限されます。
買取は原則として自らの営業所内に限定されます。
【行商しない】で申請してしまった場合
すでに『行商しない』で申請してしまっている場合についてです。
このような場合でも書換申請・変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出することで、変更が可能です。
届け出は変更があった日から14日以内に行いましょう。
書換申請・変更届出書はこちら ☞警視庁
訪問買取には様々なルールがあります。
『行商をする』で申請した場合でも、訪問買取( 法律上は「訪問購入」といいます )を行う際には、特に注意が必要です。
訪問購入は、特定商取引法により消費者保護の観点から厳格なルールが定められており、違反すると行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
主な古物商の義務としては以下のようなものがあります。
・ クーリングオフ制度の説明
・ 勧誘時に、事業者の名称・住所・連絡先を明示すること
・ 勧誘の目的および商品の概要を最初に明確に伝えること
これらの義務を怠ると、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
行商は、古物営業の可能性を広げる大きな一歩です。
ただし、そのためには法律上のルールを正しく理解し、適切に対応することが欠かせません。
きちんと備えることで、古物ビジネスの新たな展開につなげていきましょう。