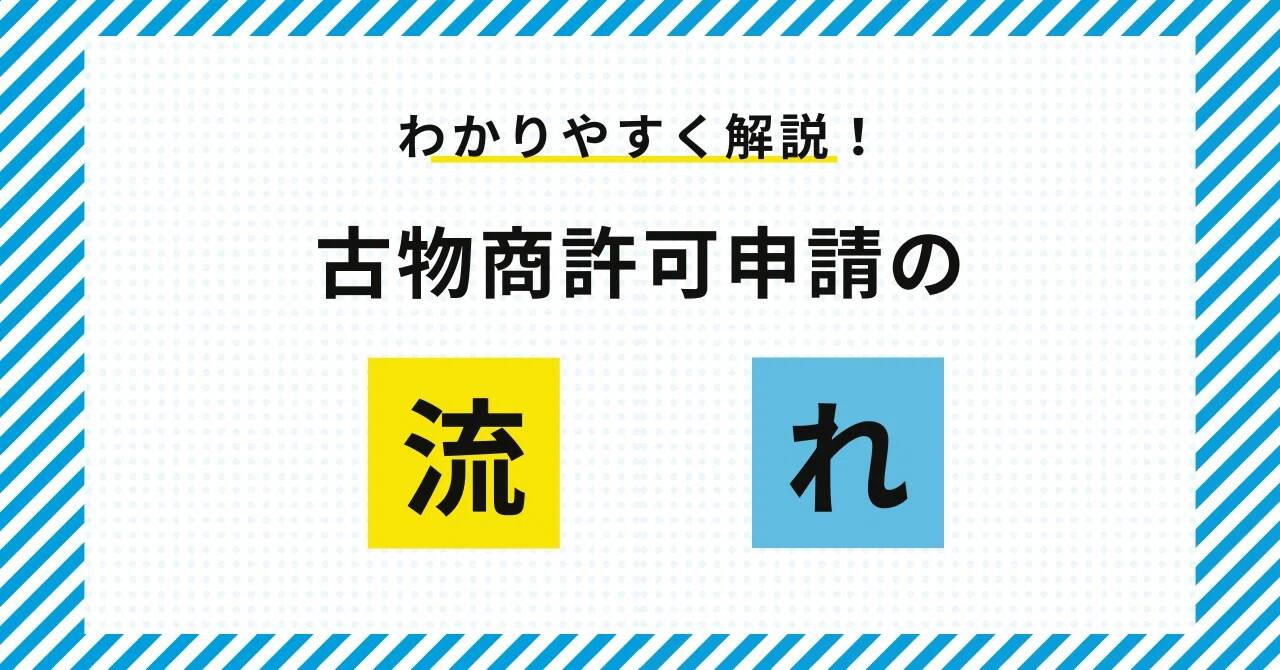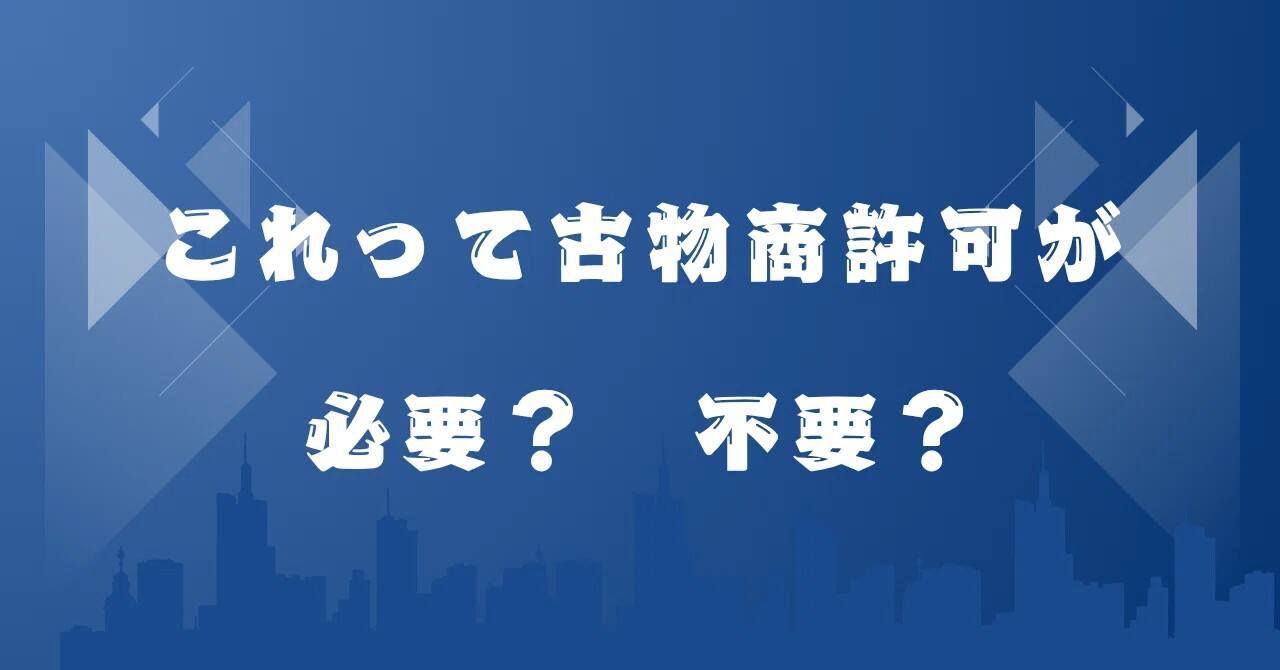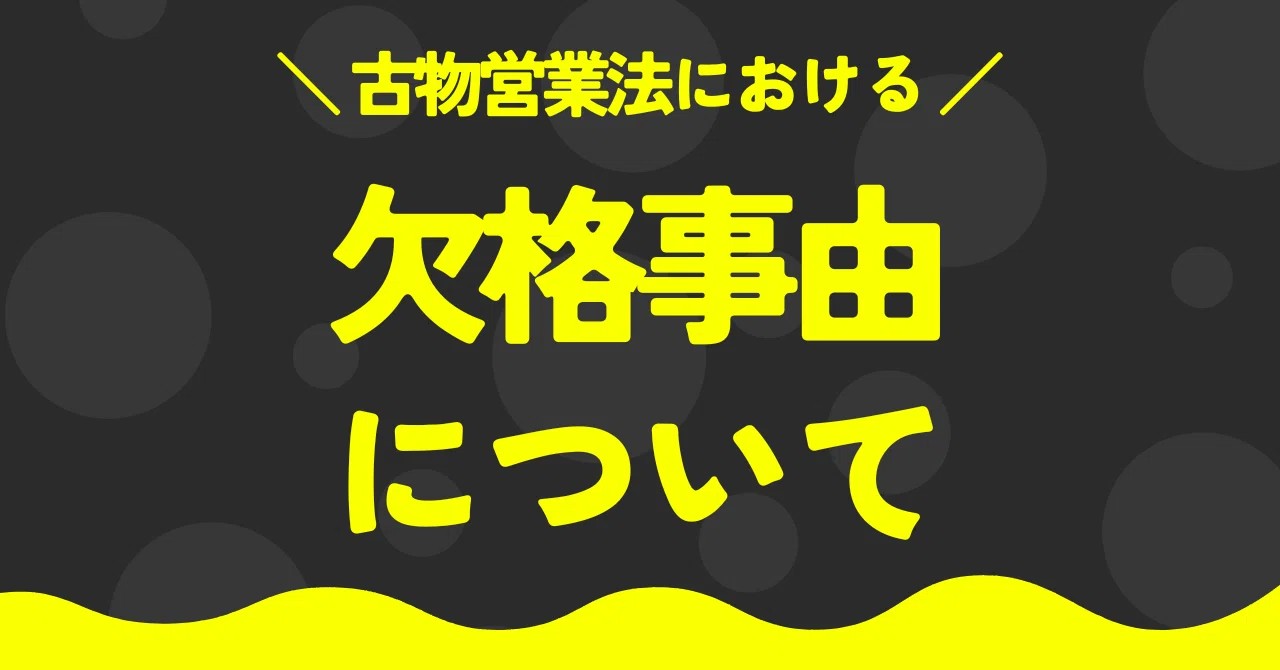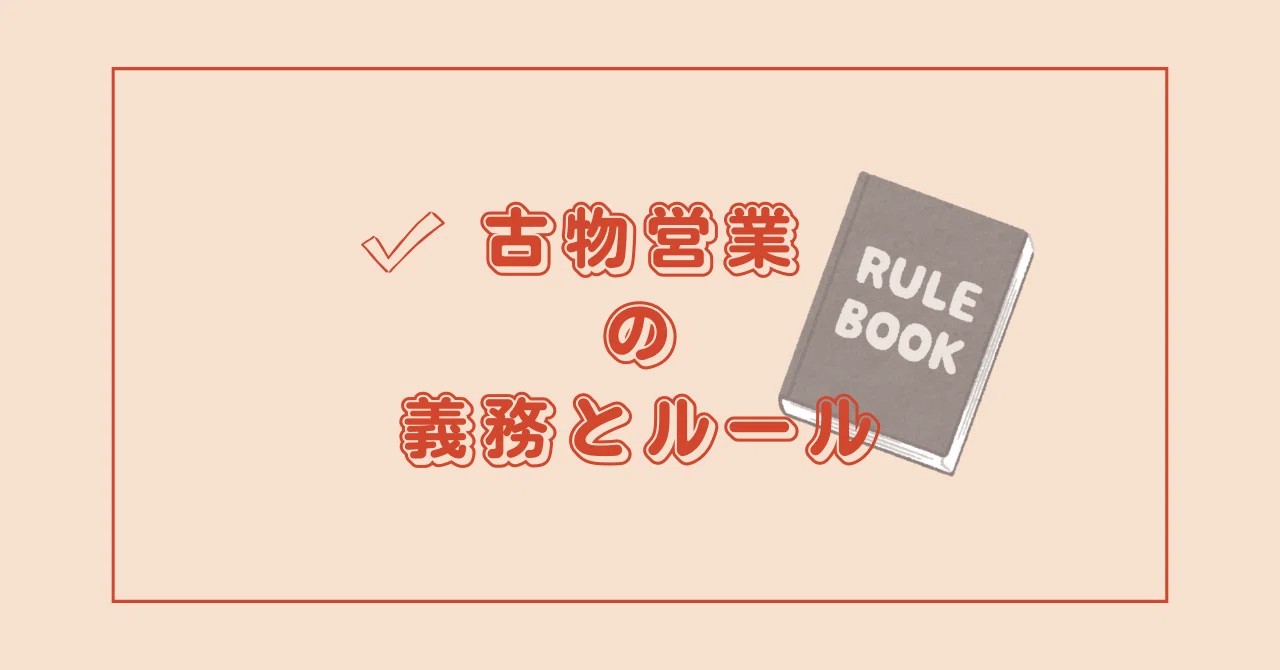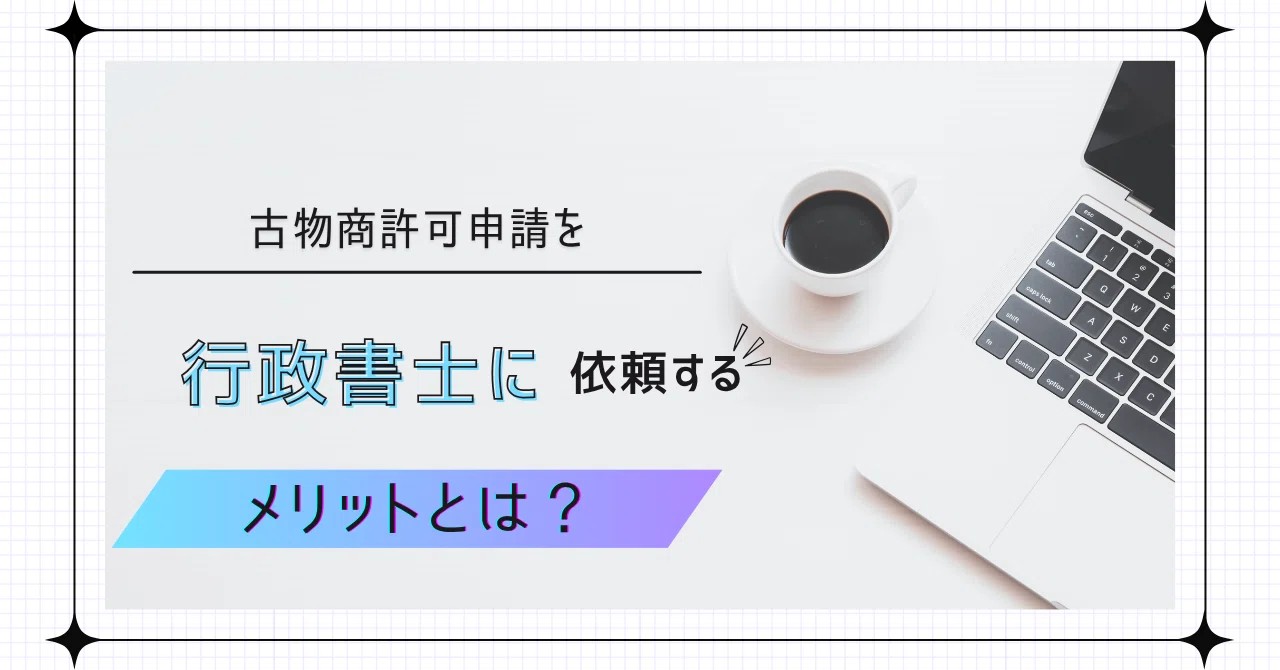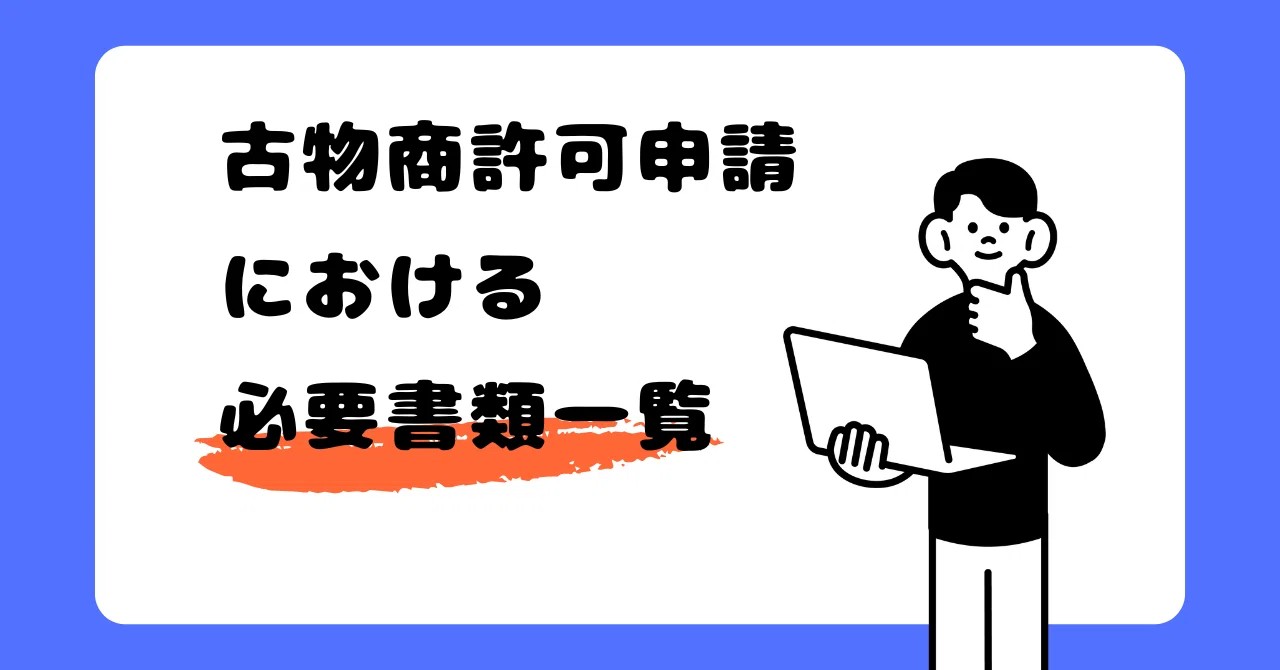非対面方式における取引での本人確認
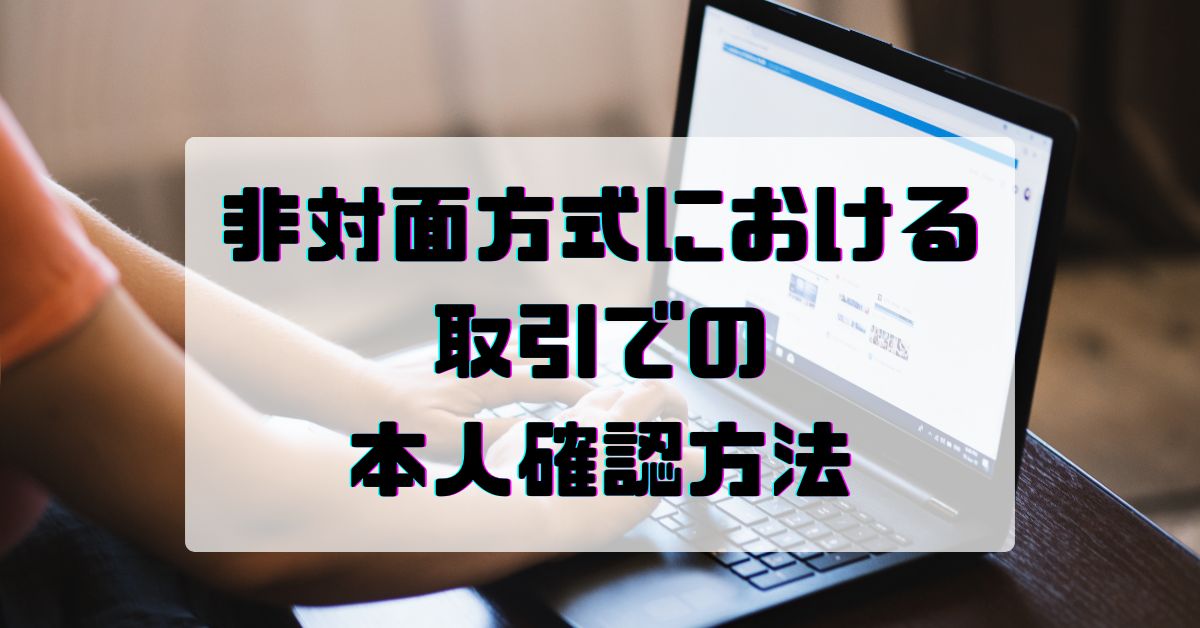
近年、フリマアプリやネットオークションの普及により、古物の取引も対面ではなくオンライン上で完結するケースが増えています。
それに伴い、古物営業においても「非対面取引」に関するルールや対応がますます重要視されるようになってきました。
古物商には、取引の際に相手方の本人確認義務が課されています。
本記事では、古物営業法における非対面での本人確認方法について、基本的な対応ポイントをわかりやすくまとめています。
これからインターネットで古物取引を始めようとしている方や、すでに実施しているものの対応に不安がある方にとって、参考となれば幸いです。
古物商の本人確認方法
非対面取引であっても、基本的には本人確認義務があります。
例外として、取引の対価の総額が1万円未満であって、かつ法令で定める「本人確認義務の免除対象となる古物以外」の品目に関しては、本人確認義務が免除されることがあります。
非対面取引における主な本人確認方法
① 電子署名されたメールを受け取る
② 印鑑証明+押印した書類をもらう
③ 本人限定受取郵便などで到着を確認
④ 本人限定受取現金書留で支払業務を行う契約
⑤ 住民票の写し等をもらい、転送しない書留で送る
⑥ 免許証やマイナンバーカードのICチップ情報を使い、転送不可で書留などを送る
⑦ 運転免許証などの鮮明な画像を、リアルタイムで撮影・送信してもらう
⑧ 免許証+補完書類のセットで確認する方法
⑨ 住民票の写し等の送付+本人名義の口座に代金振り込む契約を結ぶ
⑩ 本人確認書類コピー+口座振込をする契約を結ぶ
⑪ 動画・アプリで顔と身分証の一致を確認する
⑫ 顔写真+ICチップ内の情報を確認する方法
⑬ マイナンバーカードに入っている電子証明書を使う方法
⑭ 公的に認定された電子証明書を使う方法
参考 ☞大阪府警察
① 電子署名されたメールを受け取る
紙の書類で言えば、「手書きのサイン」や「実印」にあたるものを、データ上で行うのが「電子署名」です。マイナンバーやアプリを使用して非対面取引でも法律に適合する本人確認ができます。
参考 ☞デジタル庁
② 印鑑証明+押印した書類をもらう
取引相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢、職業記載)を送ってもらいます。その際の書類の形式は特に定まっていません。
③ 本人限定受取郵便などで到着を確認
郵便物を受け取る際に宛名人が本人確認書類を提示し、郵便物を受け取るサービスです。
通常の郵便は、家族や同居人でも代わりに受け取れますが、本人限定郵便は、『本人以外は受け取り不可』というルールがあるので、「確実に本人に届いた」と証明できるのが最大の特長です。
参考 ☞日本郵便株式会社
④ 本人限定受取現金書留で支払業務を行う契約
例えば、売主は古物商に物を郵送し、古物商は売主に本人限定郵便にした現金書留で代金を支払うことを約束した場合などです。
約束した支払方法と異なる支払方法で代金を支払う場合は改めて相手方に確認する必要があります。
⑤ 住民票の写し等をもらい、転送しない書留で送る
宛先の本人の現住所にしか届かないようにするための特別な郵送方法です。
ここでいう住民票の写し等とは、『住民票の写し』『戸籍抄本・謄本』『印鑑登録証明書』など役場が発行する各種証明書です。
転送しない取扱いとは、転居などで自動転送されてしまうと「本人確認のつもりで送ったのに、違う場所に届いてしまう」という問題が起きてしまいます。
そのため、簡易書留を送付する際、郵便物の表面のわかりやすいところに「転送不要」と表記することで、転送不要の対応をしてくれます。
⑥ 免許証やマイナンバーカードのICチップ情報を使い、転送不可で書留などを送る
ICチップには「この人が本当に本人ですよ」という証明の情報が入っています。
その情報は、秘密鍵を使って暗号化されているため、それを公開鍵で元に戻すことで、
「この情報は、ちゃんと本人が発行したもので、改ざんされていません」
ということを確認できる仕組みです。
⑦ 運転免許証などの鮮明な画像を、リアルタイムで撮影・送信してもらう
表面だけではなく厚みなどの特徴が分かるように撮影する必要があります。また、送信された画像は帳簿等とともに保存しなければなりません。
⑧ 免許証+補完書類のセットで確認
ここでいう補完書類とは、『国税又は地方税の領収証書又は納税証明書』『社会保険料の領収証書』『公共料金の領収証書』などです。
⑨ 住民票の写し等の送付+本人名義の口座に代金振り込みをする契約を結ぶ
送付されてきた住民票の写し等に記載されている本人名義の口座に代金を振り込む契約を結びます。
⑩ 本人確認書類コピー+口座振込をする契約を結ぶ
本人確認書類とは、運転免許証、国民健康保険者証等を指します。
そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結びます。
⑪ 動画・アプリで顔と身分証の一致を確認する
古物商が提供するソフトウェアを使用します。
あらかじめ撮影されていたものや、加工されているものを受け取ることはできません。
また、データを取引の記録とともに保存する必要があります。
⑫ 顔写真+ICチップ内の情報を確認する方法
古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、ICチップ情報の送信を受けます。
⑬ マイナンバーカードに入っている電子証明書を使う方法
電子証明書は個人番号の記載がないものでなければなりません。
相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受ける方法です。
⑭ 公的に認定された電子証明書を使う方法
「公的個人認証法」という法律で定められた電子証明書と電子署名をもらいます。
この電子証明書には、相手の住所、名前、仕事、年齢などの情報が入っています。
これを受け取ることで、デジタルの記録として証明されます。
以上は施行規則等で例示されている本人確認手法の代表例です。
各方式には細かい要件(到達確認の方法、データの保存、技術的要件、特定の認定者の利用制限など)があります。
詳細は最新の警察庁・都道府県警の解説を確認してください。
まとめ
非対面形式での古物取引は便利ですが、本人確認・取引の安全確保を怠ると法令違反・トラブルのリスクが高まります。
住民票・免許証・電子署名・郵送手段など、アナログ・デジタル双方の手法を適切に組み合わせて、安心・安全な取引を目指しましょう。