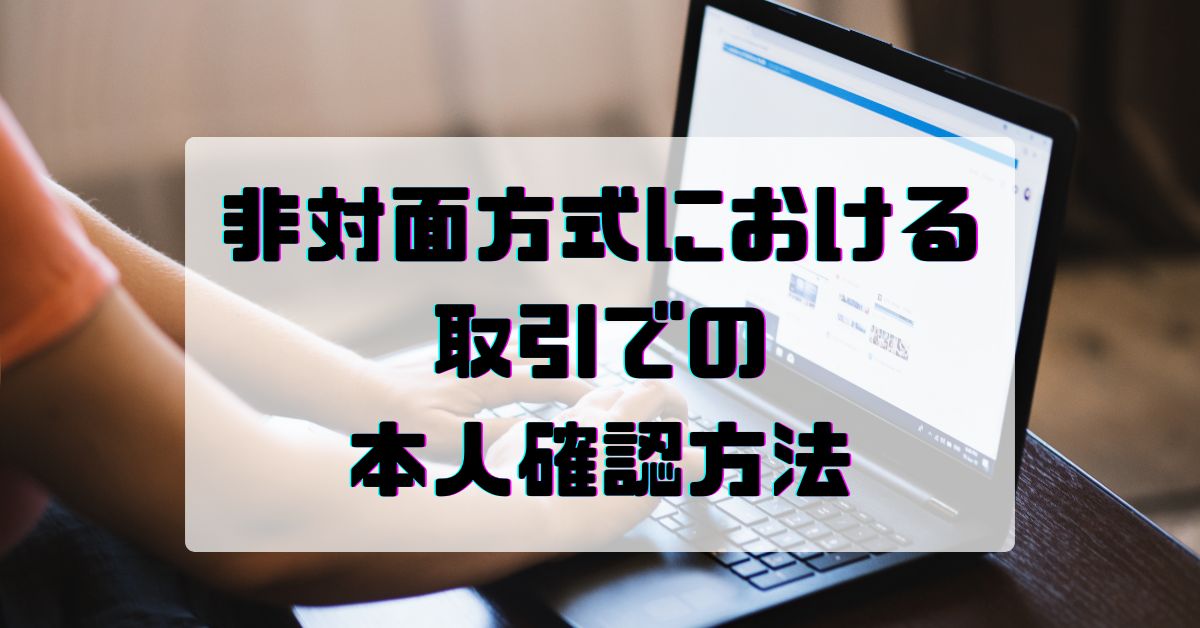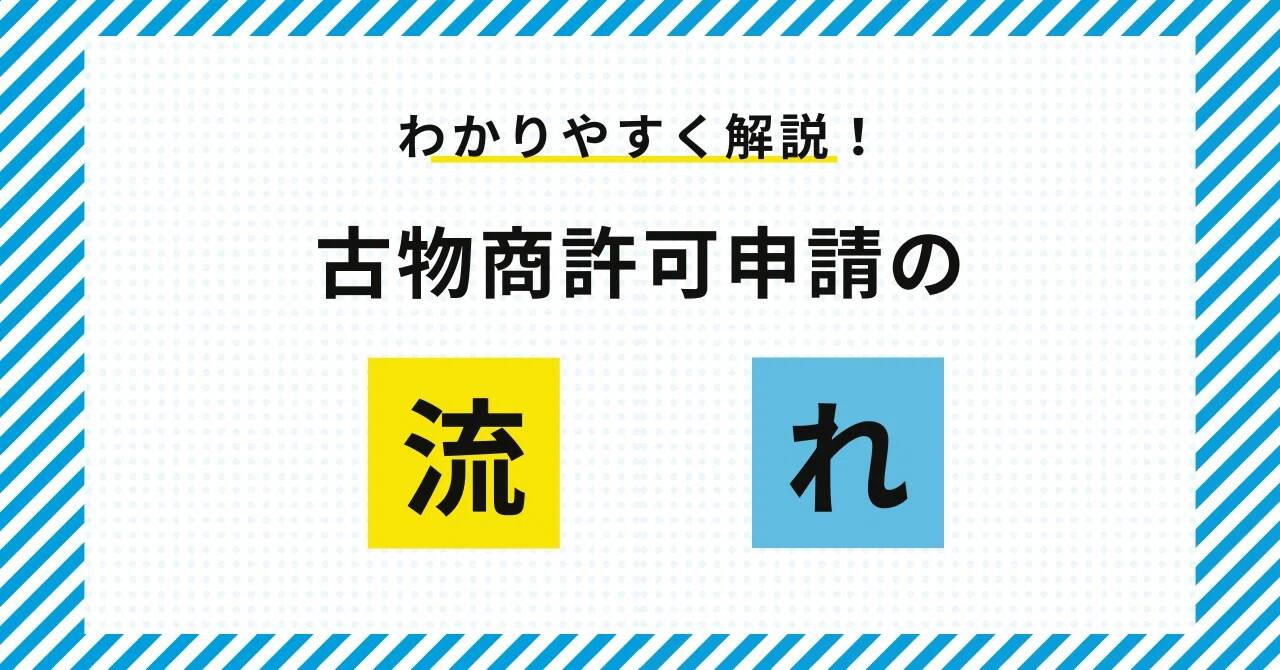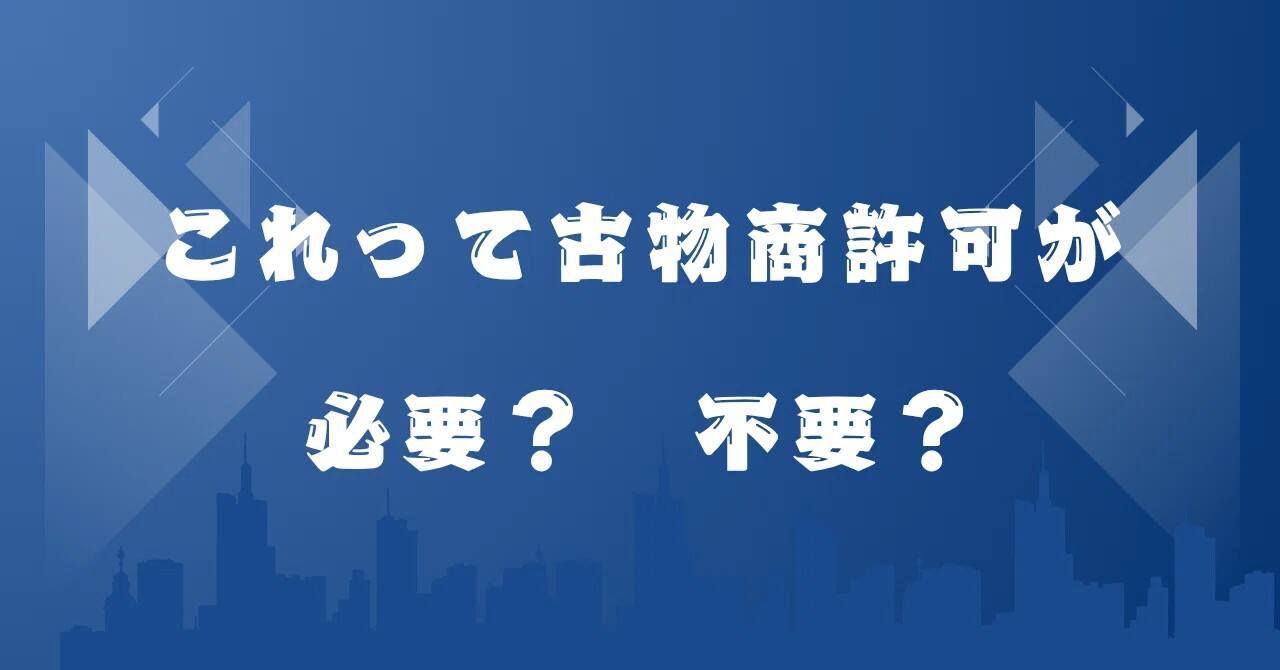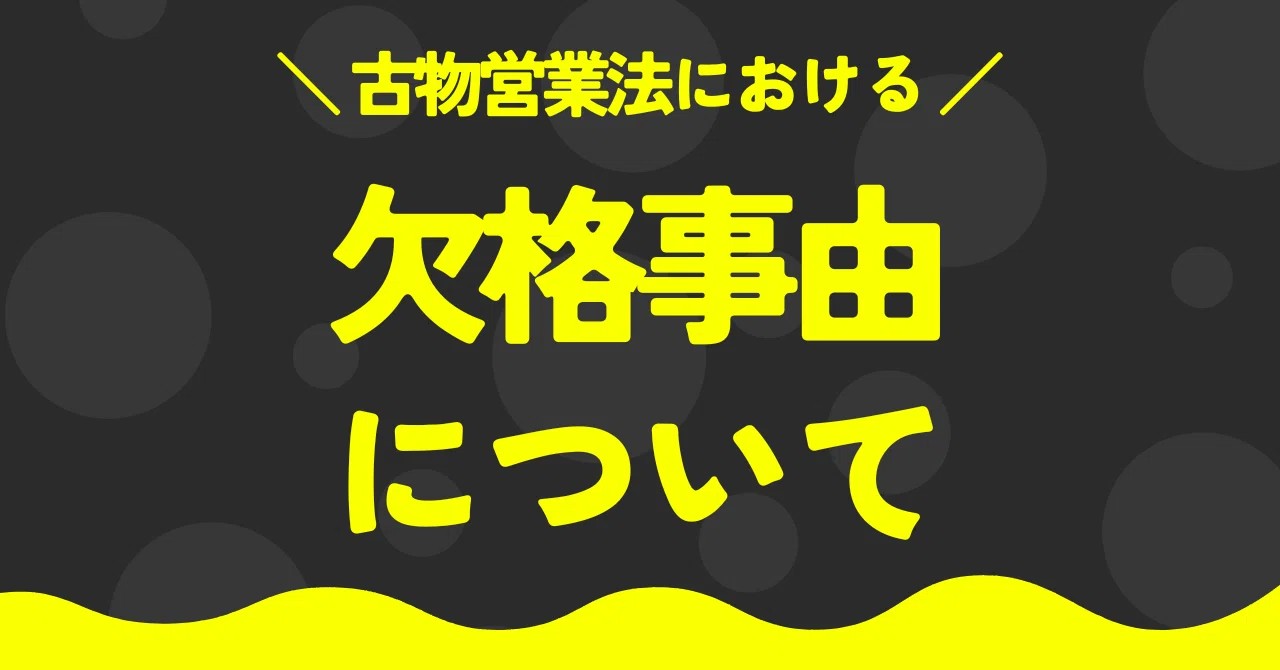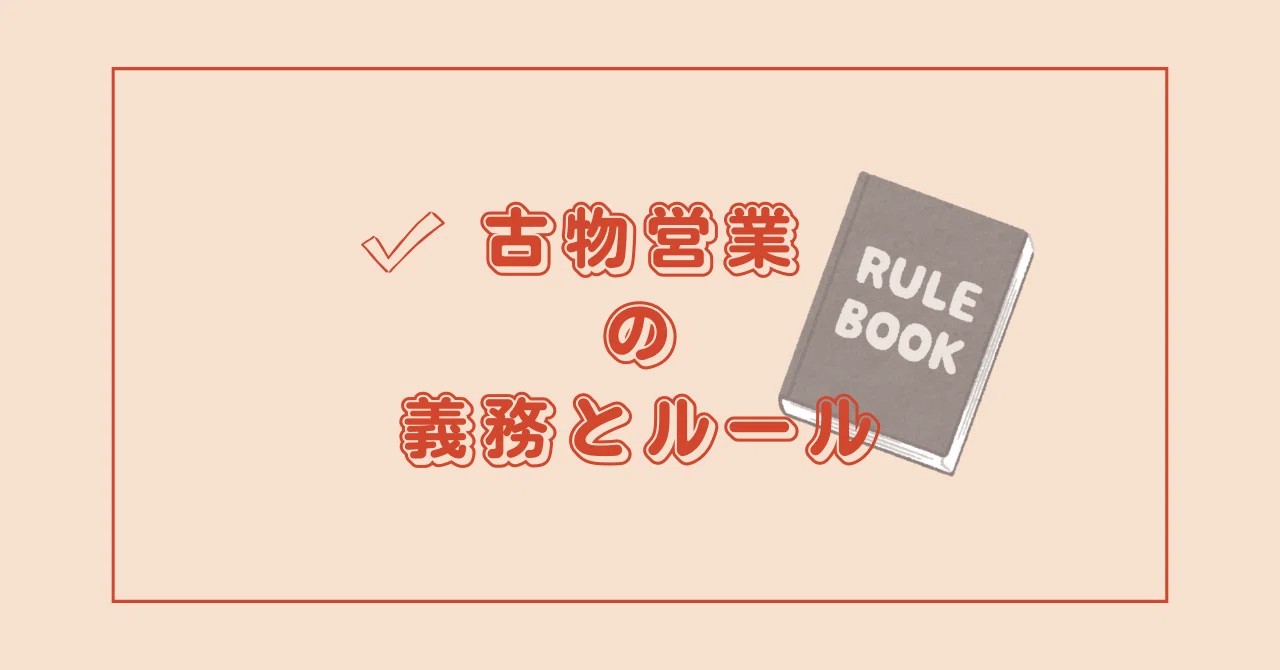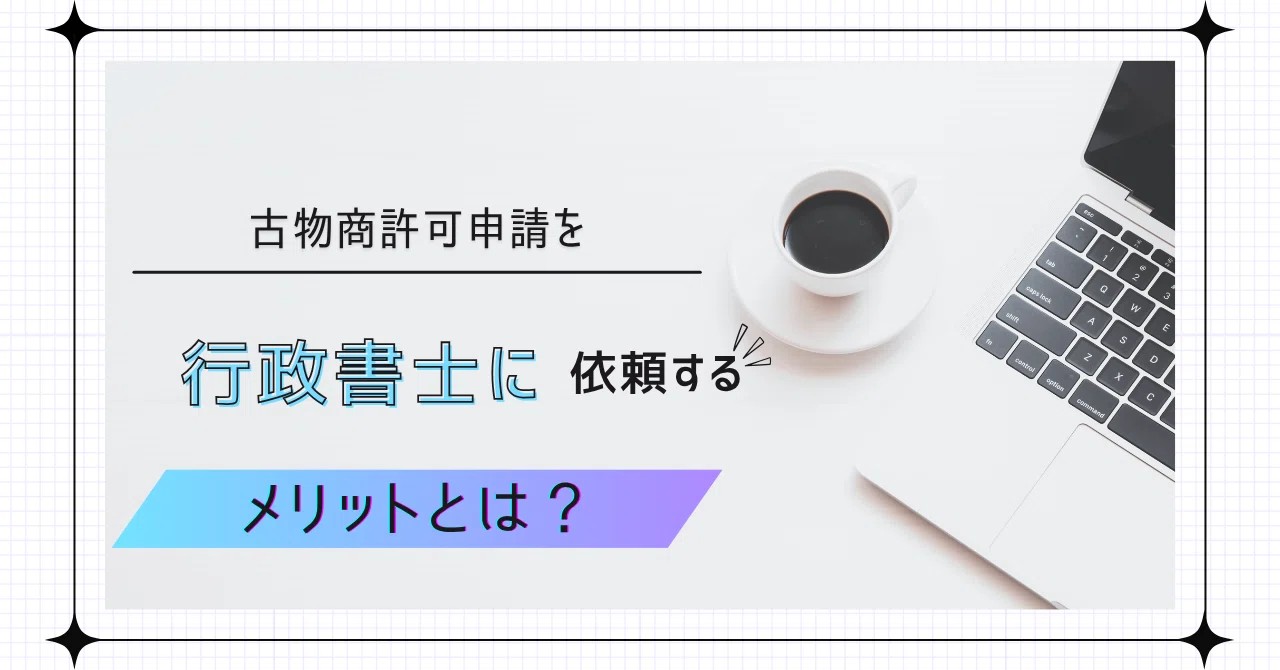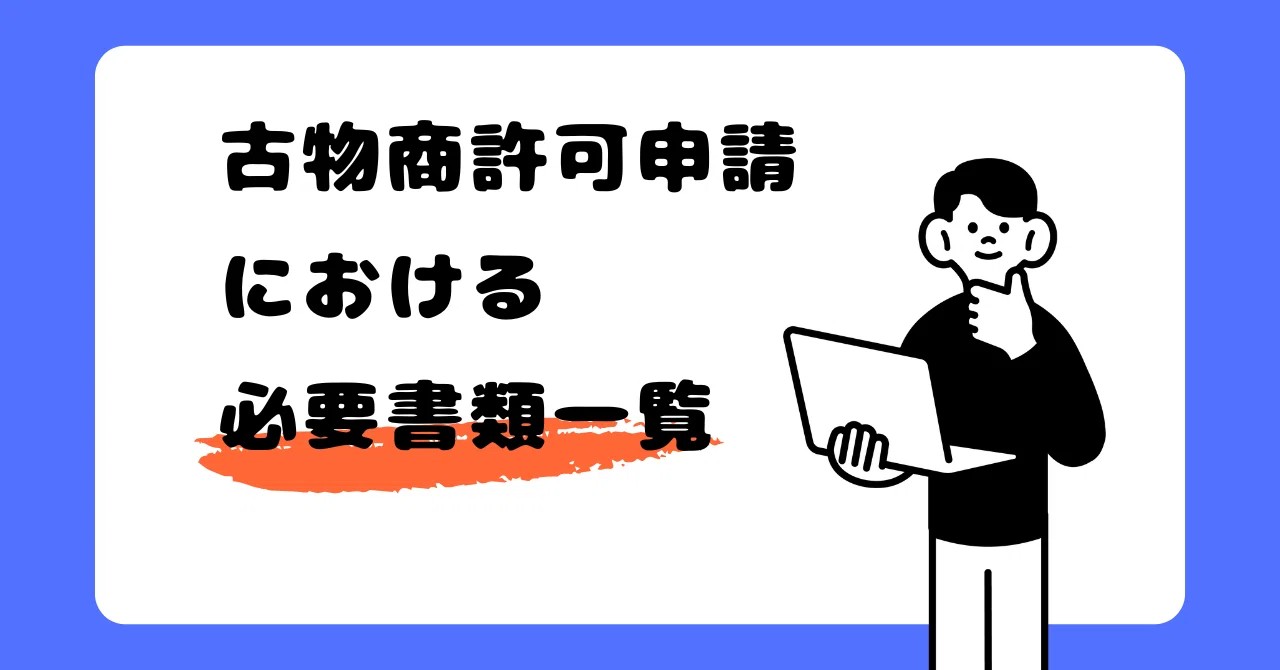本記事では、『防犯三大義務』について解説いたします。
本記事では、『防犯三大義務』について解説いたします。
古物商の防犯三大義務

防犯三大義務とは
古物商には、防犯の観点から重要な「防犯三大義務」が法律により課されています。
防犯三大義務は以下の3つから構成されます。
① 本人確認義務
② 帳簿の記録義務
③ 不正品の申告義務
「防犯三大義務」の目的は、盗品などの不正品の売買を防止し、迅速な発見と対応を図ることで、窃盗などの犯罪を未然に防ぎ、被害の早期回復に貢献することにあります。
また、万が一、不正品(盗品など)を買い取ってしまった場合には、被害者から民法上の返還請求を受ける可能性があります。
その結果、古物商としては仕入れた物品を失うだけでなく、営業上の損失を被る恐れもあります。
このようなリスクを回避するためには、不正品を適切に見極め、疑わしい物品は買い取らないことが重要です。
そして、もし買い取った後に盗品などの可能性が判明した場合は、速やかに警察に申告し、法に則った対応を取る必要があります。
古物商の防犯三大義務の概要
防犯三大義務について一つずつ確認していきます。
① 本人確認義務
古物商が物品を買い取る際、取引相手が誰であるかを確認する義務です。これは、盗品が売り込まれるのを未然に防ぐことを目的としています。
具体的には、古物の取引を行う際、相手が「誰」であるか、「どこに住んでいるか」などの情報を、身分証明書などにより確認する必要があります。
確認対象は個人だけでなく、法人(会社)も含まれます。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、などが有効な確認書類となります。
顔写真があるものが好ましいです。
またインターネット上での取引のような非対面式での取引でも本人確認は必須です。
この確認を怠ると、古物商自身が盗品の流通に関与してしまうリスクがあり、法的責任を問われる可能性があります。
② 帳簿の記載義務
古物の取引内容を詳細に記録し、帳簿(または電磁的記録)として保存しておく義務です。
記録する内容には、以下のようなものが含まれます。
・取引年月日
・古物の品目・特徴(種類、状態など)
・数量
・相手方の氏名・住所・職業・年齢など
・本人確認書類の種類および番号
※マイナンバーカードや健康保険証に記載されている一部の情報については、記録・コピー・書き写し等が禁止されているため注意が必要です。
これらの記録は、万が一盗難品が取引された場合、警察が迅速に調査を進めるための重要な手がかりになります。
帳簿は取引から3年間保存する必要があります。
電子化も認められていますが、その場合も必要な情報を漏れなく記録することが求められます。
③ 不正品の申告義務
第三の義務は、「この品物は盗品ではないか」「正当な所有者からの提供ではないのでは」といった疑いがある場合に、直ちにその旨を警察官に通報することが義務づけられています。
具体的には、
・挙動不審
・購入場所、商品知識などが曖昧である
・遠隔地から持ち込んで来た人や個人なのに頻繁に来る人
・同じものを大量に持ち込む
・製造番号やシリアルナンバーが消されている
など、通常と異なる事情があれば、警察に通報する、買取を保留にするなどの対応が求められます。
この義務は、盗品を取得してしまうことを防ぐためのもので、古物商には慎重な判断と対応が期待されています。
まとめ
以上のように、古物商に課される防犯三大義務は、単なる法的ルールではなく、社会の安全と信頼を守るための重要な責務です。
日々の業務の中でこれらの義務を正しく理解し、着実に実践することが、健全な取引の維持と不要なリスクの回避につながります。
適切な対応を心がけ、安心して利用される古物市場づくりに努めてまいりましょう。