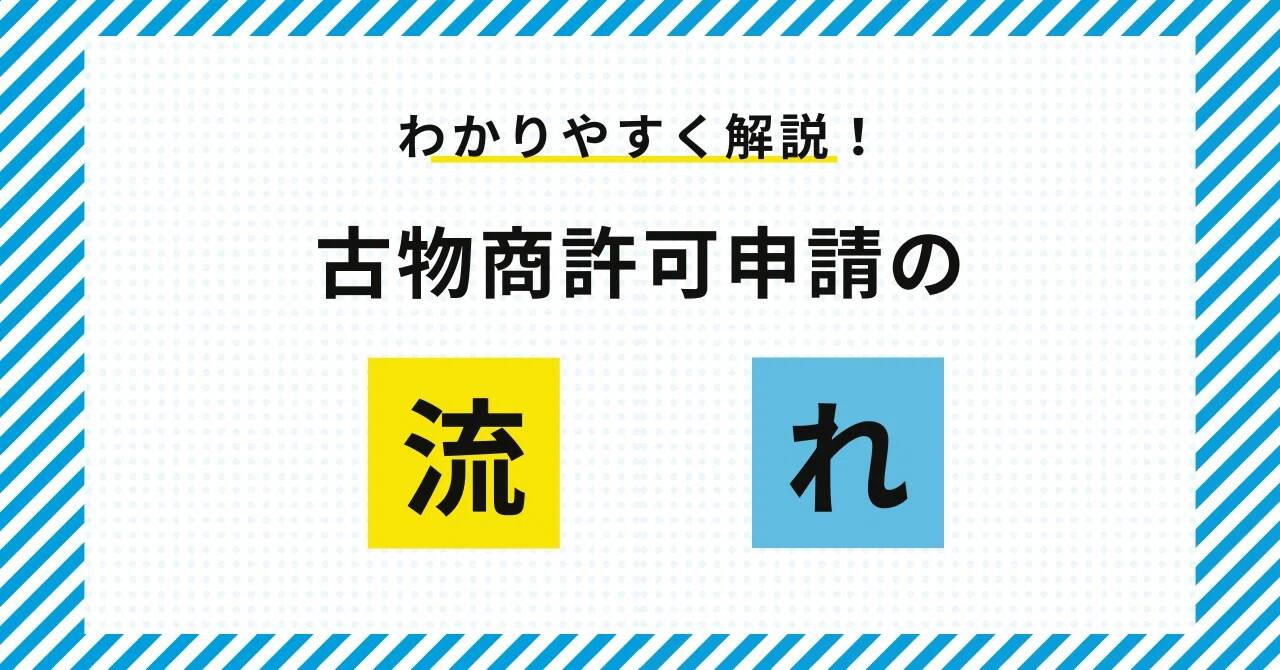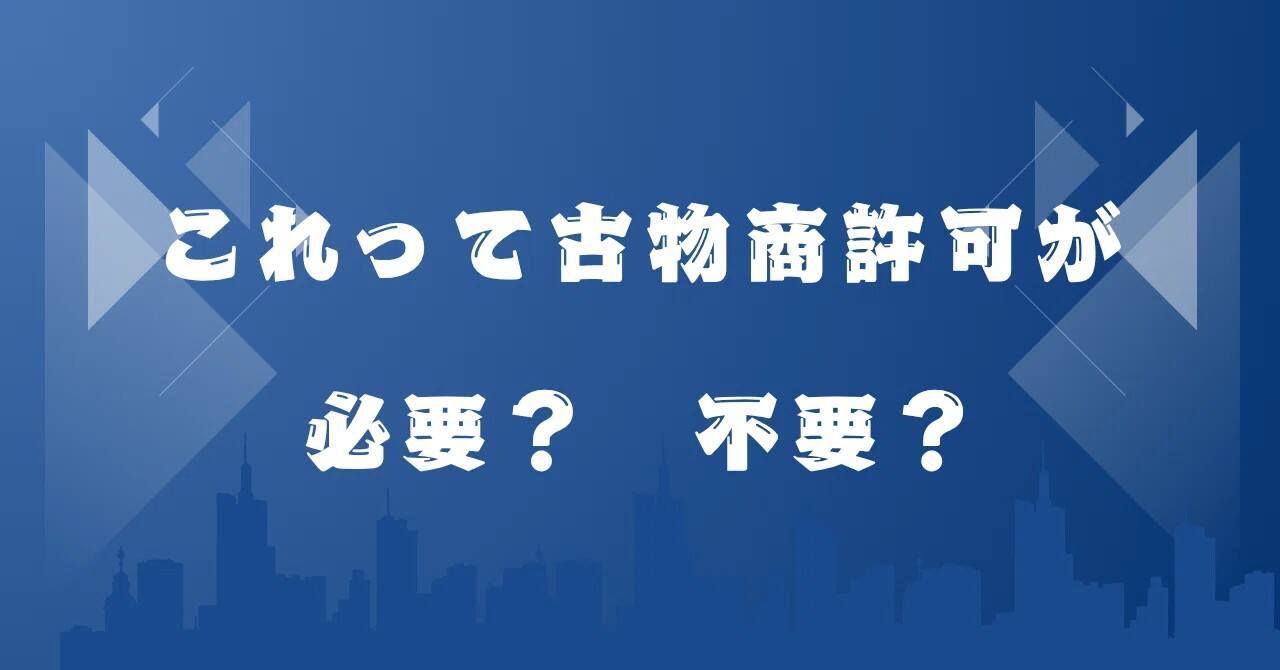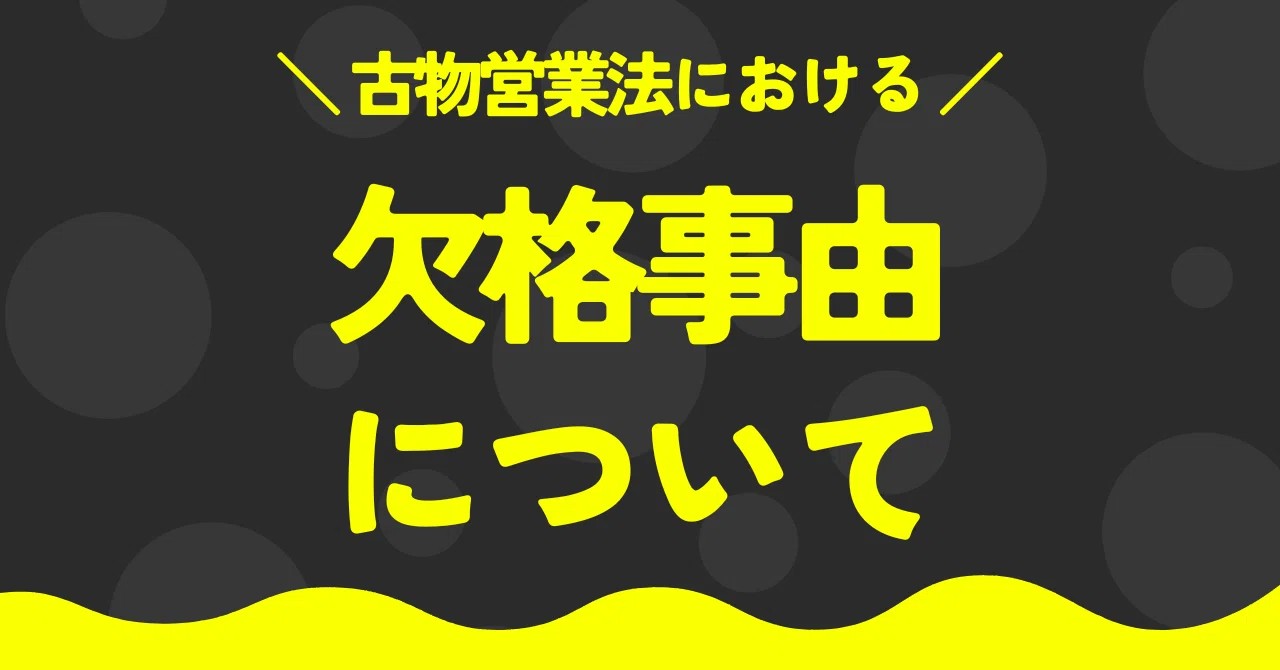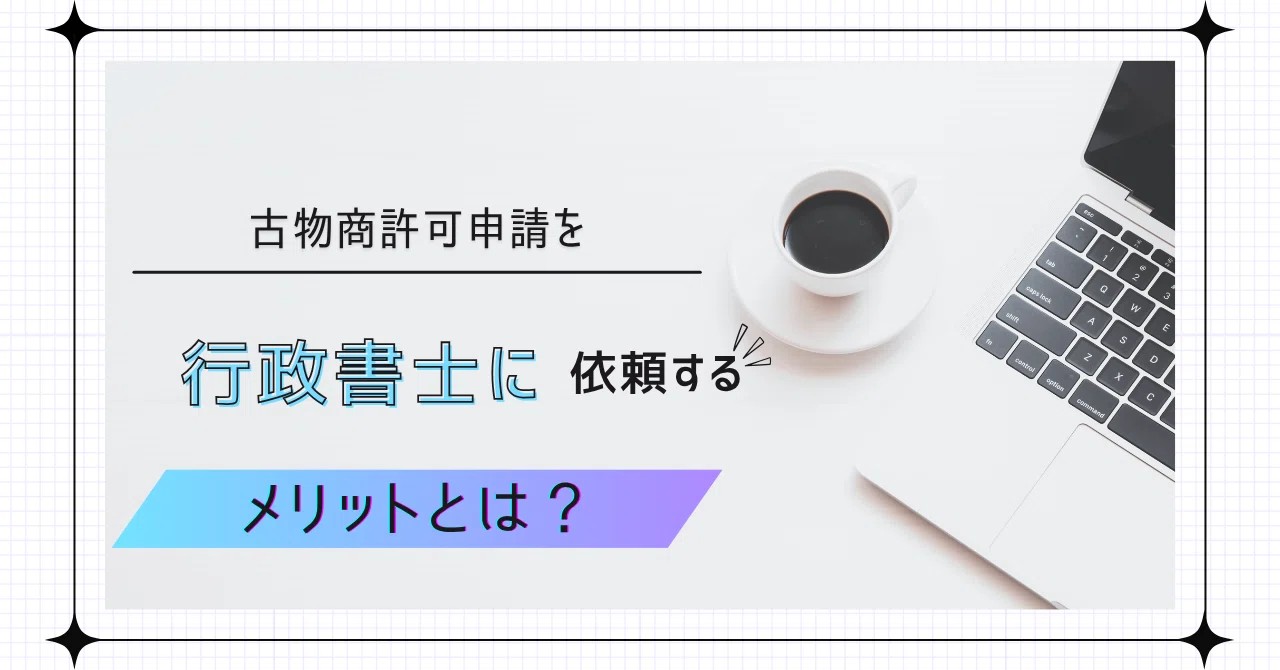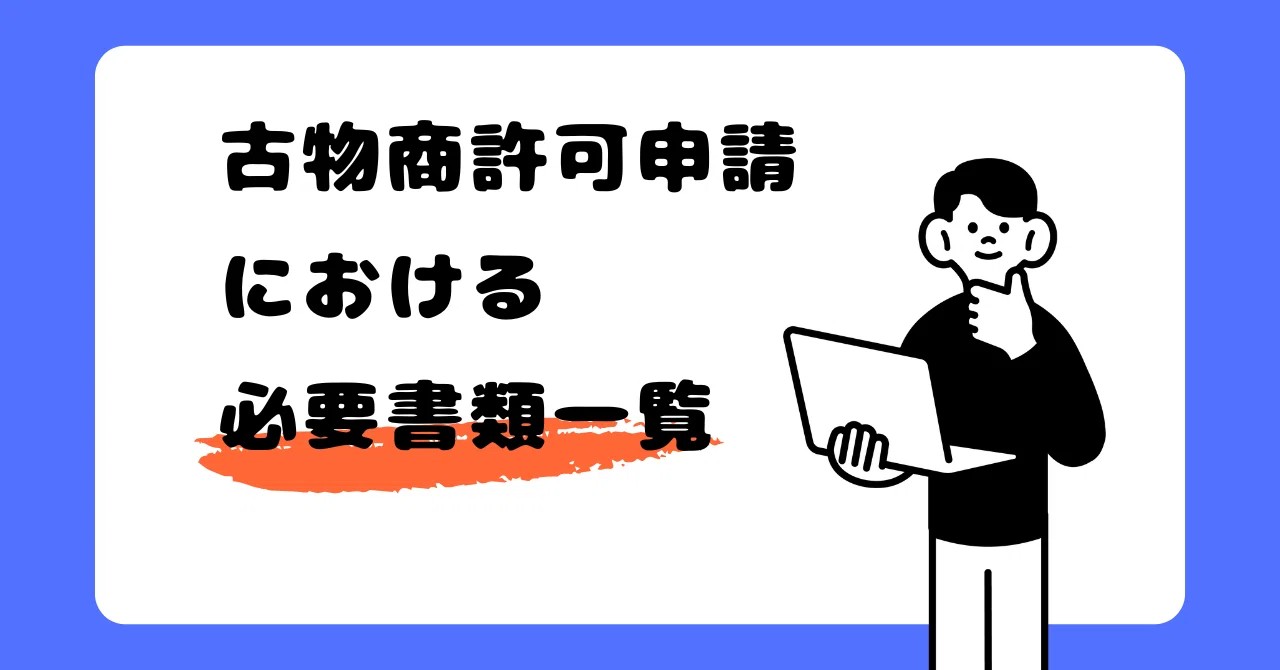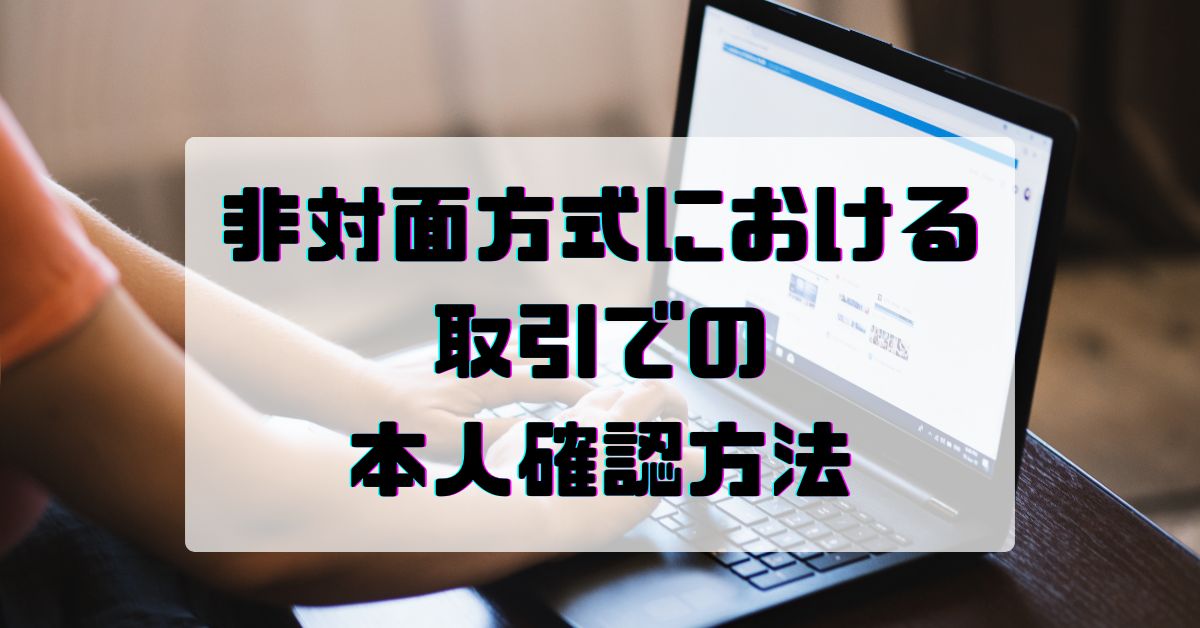古物営業の義務とルール
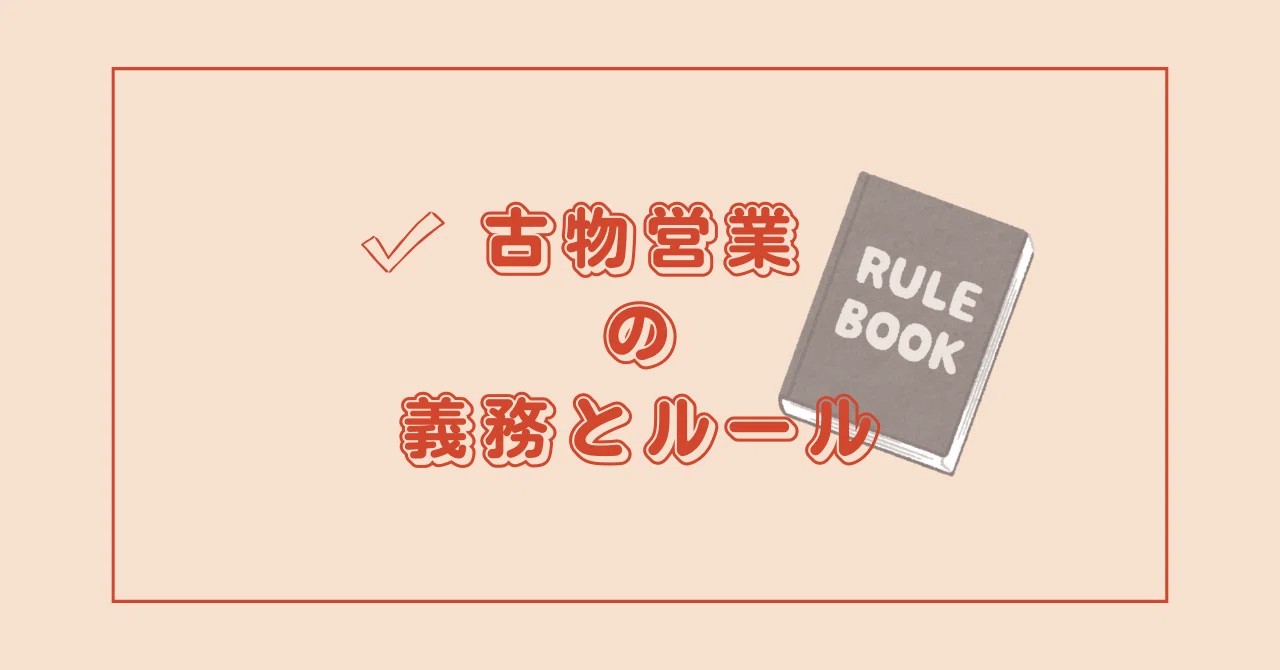
古物営業法において古物商には様々な義務が課されています。
ここでは特に重要な古物商の義務についてわかりやすく解説していきたいと思います。
① 許可を取得しましょう
どんなにリサイクル魂が熱くても、古物を取り扱う際は、許可(公安委員会のお墨付き)がないと営業できません。
違反することで罰則や行政処分を受ける可能性があります。
根拠:古物営業法 第3条(許可制)
② 標識は、しっかり掲げましょう
営業所には「ここはちゃんとした古物商です!」と標識を掲げる必要性があります。
インターネットでのみ営業をする場合でも、営業所での標識提示が義務付けられています。
根拠:古物営業法 第12条(標識の掲示等)
③ 正しく帳簿を記録・保存しましょう
古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、「帳簿等」に記載をしましょう。
また、古物商は、帳簿等を最終の記載をした日から三年間直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければなりません。
いつでも提示できるように丁寧に保存しましょう。
根拠:古物営業法 第16条〜第18条(帳簿への記載等)
④ 本人確認をしっかり確認しましょう
古物営業法の目的は、必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することです。
そのため、取引に盗品等が紛れ込まないように取引相手の本人確認が義務付けられています。
根拠:古物営業法 第15条(確認等及び申告)
⑤ 警察と協力しましょう
警察の「ちょっと見せてね」には「はいどうぞ」で対応しましょう。
立入検査を拒否または妨害した場合、処罰の対象になることもあります。
根拠:古物営業法 第22条(立入り及び調査)
⑥ 営業の住所、名前が変わったら届出しましょう
引っ越し、社名変更、店長交代。
そんな時はきちんと警察にお知らせしましょう。
根拠:古物営業法 第7条(変更の届出)
⑦ 営業する地域の条例を把握しましょう
基本的なルールは古物営業法で定められていますが、具体的な基準等は都道府県条例が適用される部分もあります。
地域が違うだけで特定品目に対する取り扱いが変化することもあります。ローカルルールをよく把握しましょう。
根拠:地方条例
⑧ 「管理者」を設置しましょう
お店には必ず「管理者」を置きましょう。
営業所が複数ある場合は営業所ごとに管理者を設置しましょう。
根拠:古物営業法 第13条(管理者)
⑨ 許可証は携帯しましょう
営業所以外の場所で取引をする際には、許可証を携帯しましょう。
提示の求めがあれば提示しましょう。
根拠:古物営業法 第11条(許可証等の携帯等)
⑩ 名義を貸して他人に営業させることはやめましょう
古物商許可はあなたに古物営業をすることを許す許可制です。
名義貸しはやめましょう。
根拠:古物営業法 第9条(名義貸しの禁止)
⑪営業には制限があります
申請時の条件によりますが、古物取引の場所は『営業所』や『相手方の住所』など制限されています。
制限を守りましょう。
根拠:古物営業法 第14条(営業の制限)
⑫ 欠格事由に該当しないこと
許可を持っていても、暴力団関係者になったり、禁錮以上の刑に処された場合など、欠格事由に該当すると許可が取り消される可能性があります。
根拠:古物営業法 第4条(許可の基準)
⑬ 個人情報は適切に管理しましょう
古物商が扱う顧客の個人情報は、個人情報保護法の対象となります。適切に保管・管理することが求められます。
根拠:個人情報保護法
まとめ
古物営業法は、一言でいえば「盗品が安易に流通しないようにするための仕組み」です。
この法律をしっかり守ることで、中古品を安心して売買できる環境が保たれ、健全で安全な中古市場を築くことができます。
正しく取り組むことで、安心して古物商としての活動をすることができるでしょう。