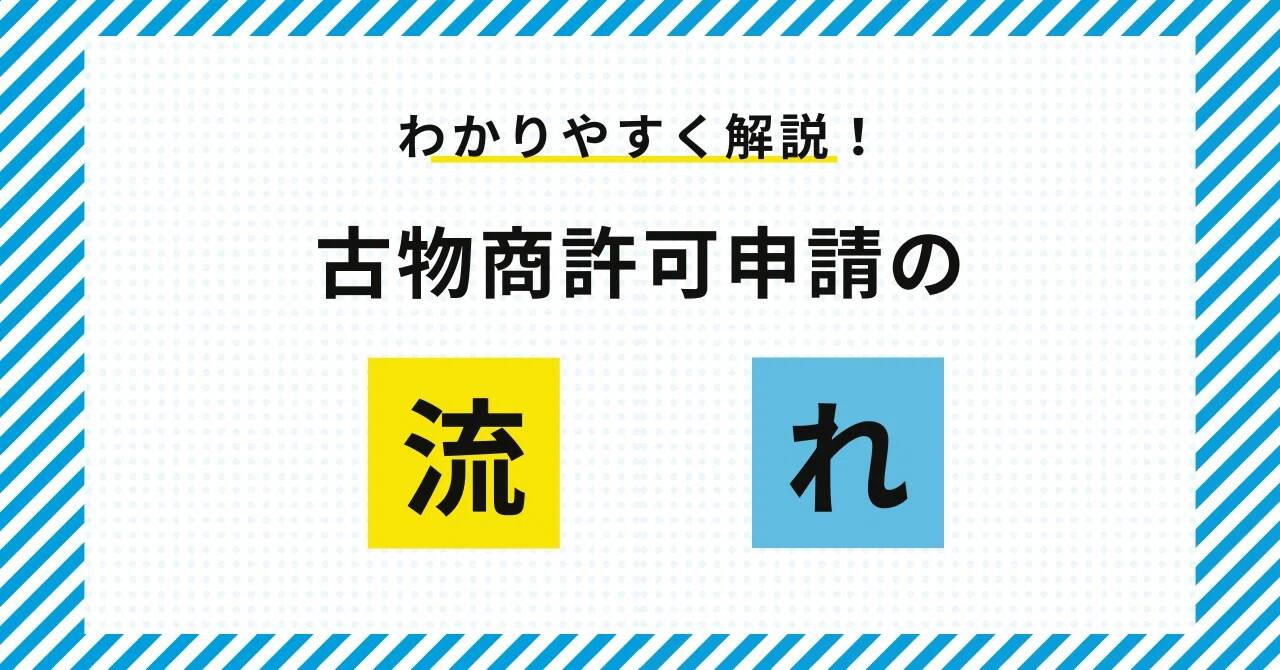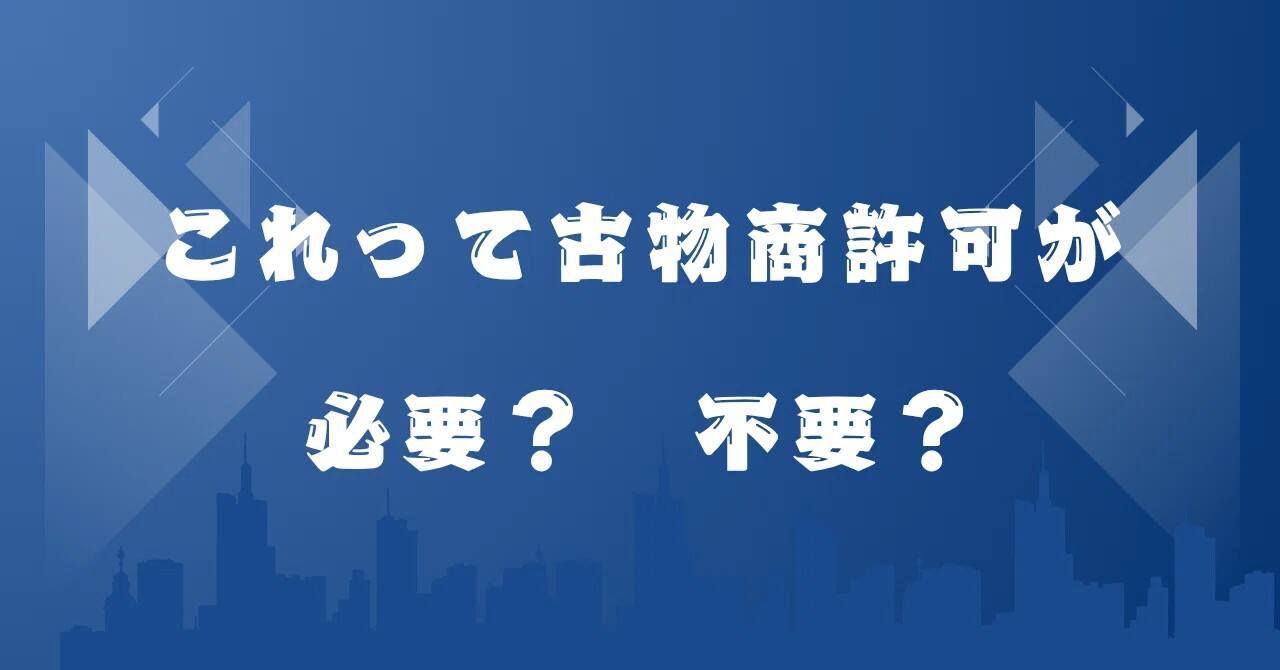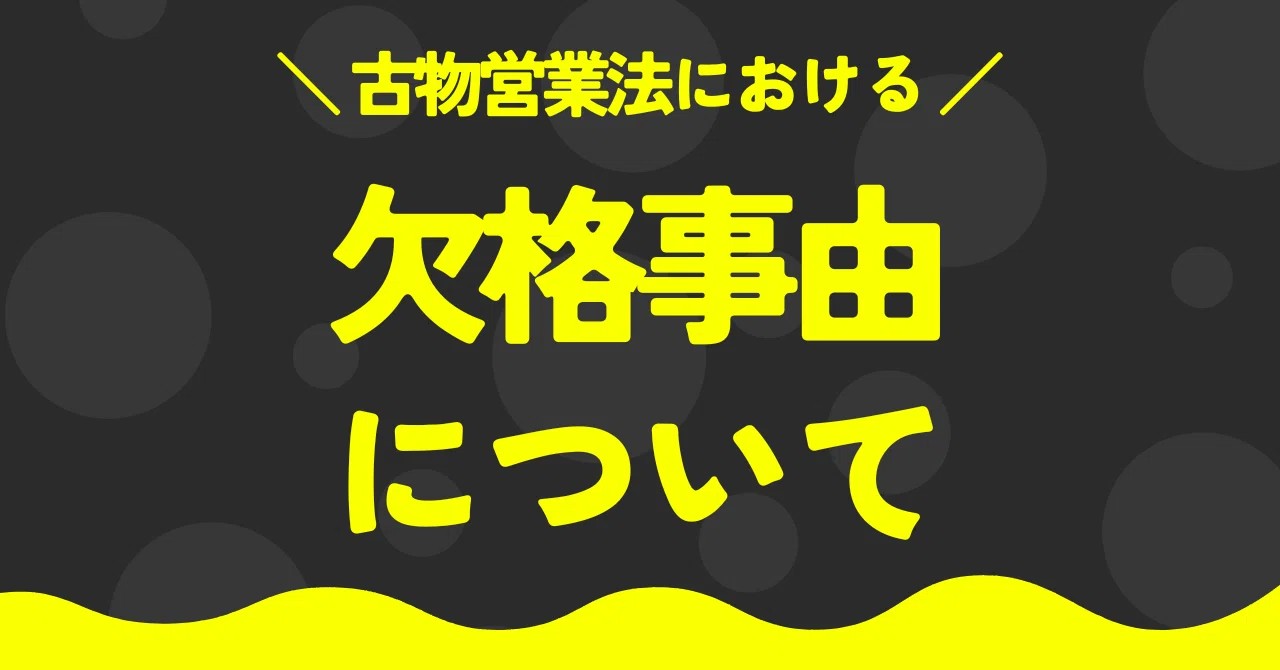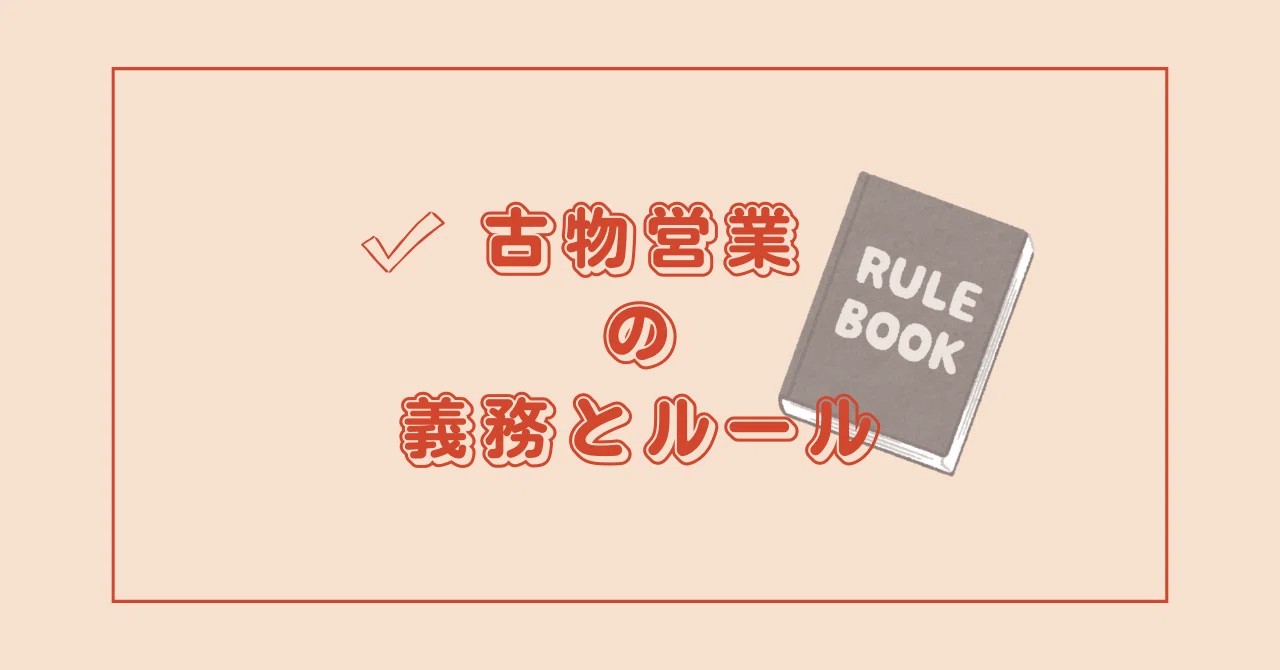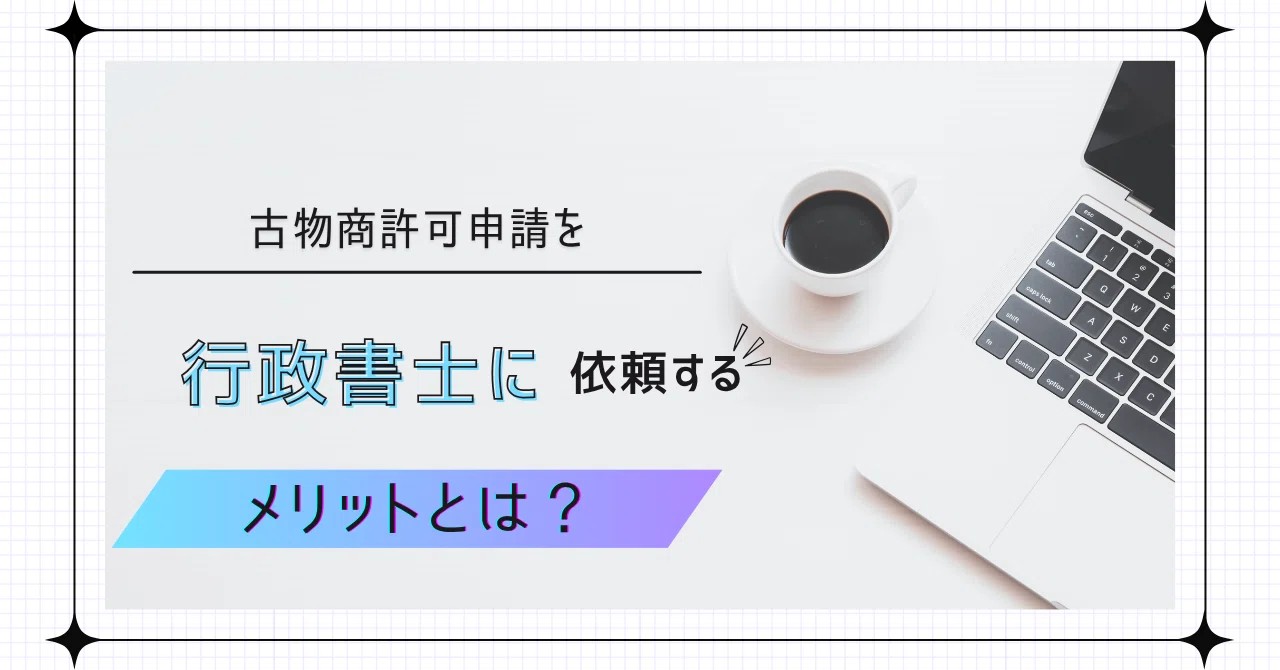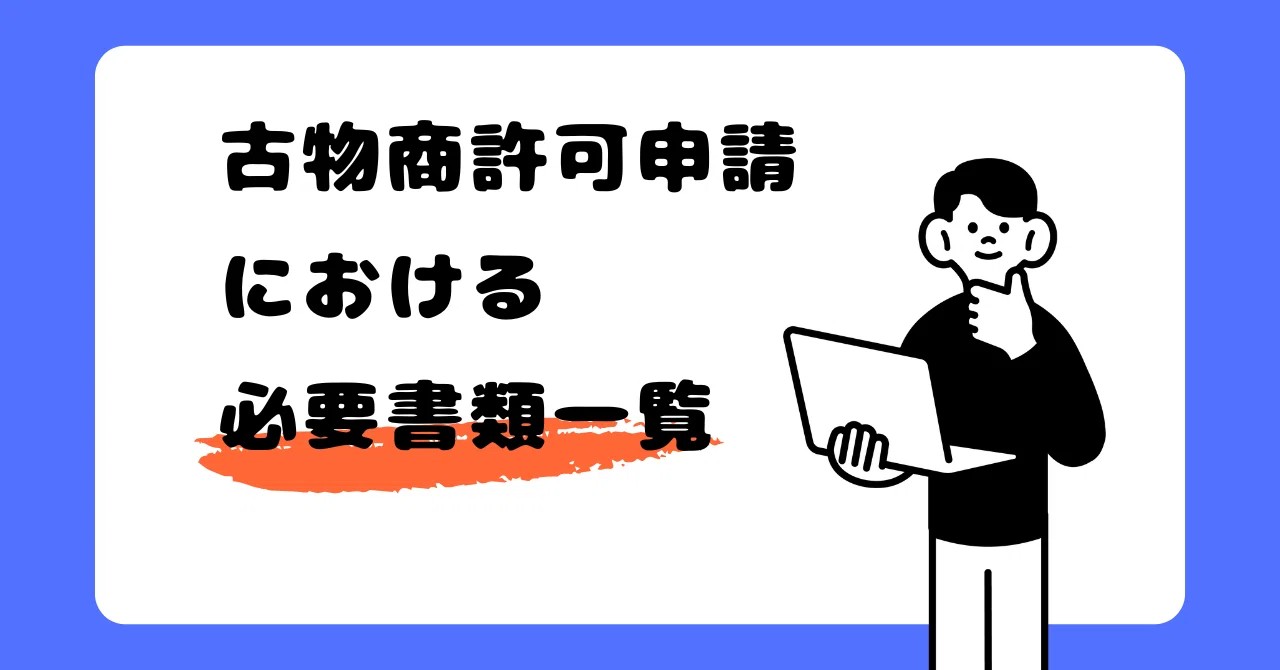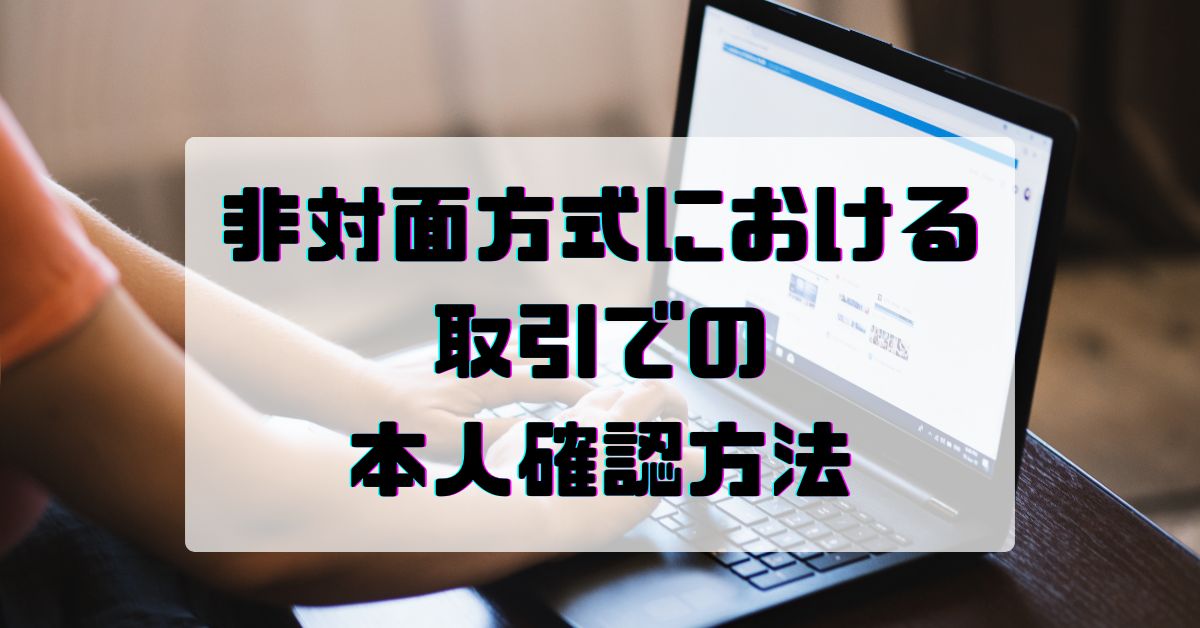古物商許可申請の流れ
今回はどのようにして古物商許可申請をするのか、一連の流れを解説していきたいと思います。
大まかには以下の通りです。
①要件の確認
②個人申請・法人申請を選択する
③取り扱う品目の決定
④必要書類の収集
⑤申請書類等の作成
⑥警察署にて申請および手数料納付
⑦審査
基本的にはこのような流れで進んでいきます。
以下では上記の①から⑦までをより詳細に解説します。
各段階の解説
① 要件の確認(欠格事由や管理者の確認)
次のような人は、古物商の許可を取ることができません。
1.暴力団の人またはその関係者
たとえ所属していなくても、その恐れがあると認められるだけで欠格自由に該当します。
2.住所がない人
住所がはっきりしていない方。
3.過去に古物商の許可を取り消されたことがある人(5年以内)
古物営業法で許可を取り消されてから5年がたっていない場合など。
4.法律的に判断能力がないとされた人や、破産して復権していない人
・成年被後見人
・被保佐人
※被補助人は該当しません。
・破産して、まだ復権していない人
5.一定の犯罪歴がある人
次のような罪で、罰を受けてから5年たっていない人は対象外です。
・禁錮以上の刑
※執行猶予の場合は執行猶予期間の満了の翌日から許可を受けることができます。
・古物営業法に違反した人(名義貸や不正に許可を取得するなど)
・背任、遺失物の横領、盗品の売買などの罪
6.選任した管理者が欠格要件に該当している場合や選任した管理者が適任でないと認められた場合
7.未成年者
法定代理人(多くの場合は親)の許可をえていない未成年者
8.法人の中に、上の1~5にあてはまる役員がいる場合
会社の役員に欠格事由のある人が1人でもいると、法人として許可を取れません。
② 個人申請・法人申請を選択する
個人で申請:個人名で許可を取得(個人事業主など)
法人で申請:会社名義で申請。登記簿謄本や役員全員の書類が必要です。
※法人での申請は、役員全員が欠格事由に該当しない必要があります。
③ 取り扱う品目の決定
古物は13品目に分類されており、主に以下のカテゴリから選びます(複数選択可)
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
※営業する業態によって必須の品目が異なります。
④必要書類の収集
役所などで必要書類を集めます。面倒な場合は行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに進みます。
⑥ 申請書の作成
•警察庁ホームページや都道府県警のホームページでダウンロードできます。
•管轄警察署で配布している場合もあります。
•記入内容には正確性が求められます。
⑦警察署にて申請および手数料納付
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。
オンライン化が進む昨今でも、古物商においては厳格な本人確認や書類審査が求められるため、原則として申請者本人が直接警察署へ足を運ぶ必要があります。
書類作成や申請手続きを行政書士に依頼すれば、面倒な手続きの多くを代行してもらうことが可能です。
•申請手数料:19,000円(収入証紙または現金)
⑧ 審査(標準処理期間:約40日以内)
•営業所の実地調査が入ることもあります。
•申請者や役員の経歴、営業所の適格性などが審査されます。
⑨ 許可証の交付 → 営業開始
•許可が下りたら、古物商許可証を受け取ります。
•許可番号を記載した標識を営業所に掲示して営業を始められます。
まとめ
ここまでご覧いただき、
「思ったより手続きが多くて大変そうだな」と感じた方もいれば、
「これくらいなら自分でやれそう!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
申請される方の状況やお考えは人それぞれです。
もし少しでも「自分だけで進めるのは不安だな」「プロのサポートを受けたいな」と感じられた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お一人おひとりに寄り添いながら、お客様にとって最善の形で許可が取得できるよう、全力でサポートいたします。