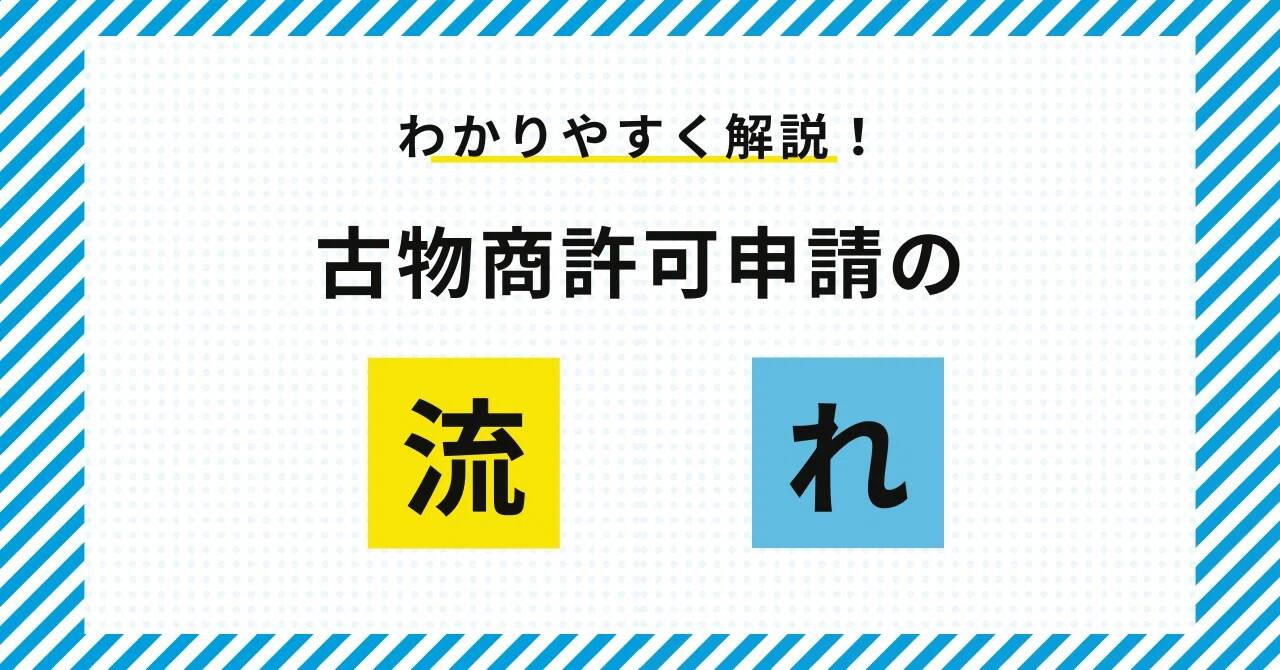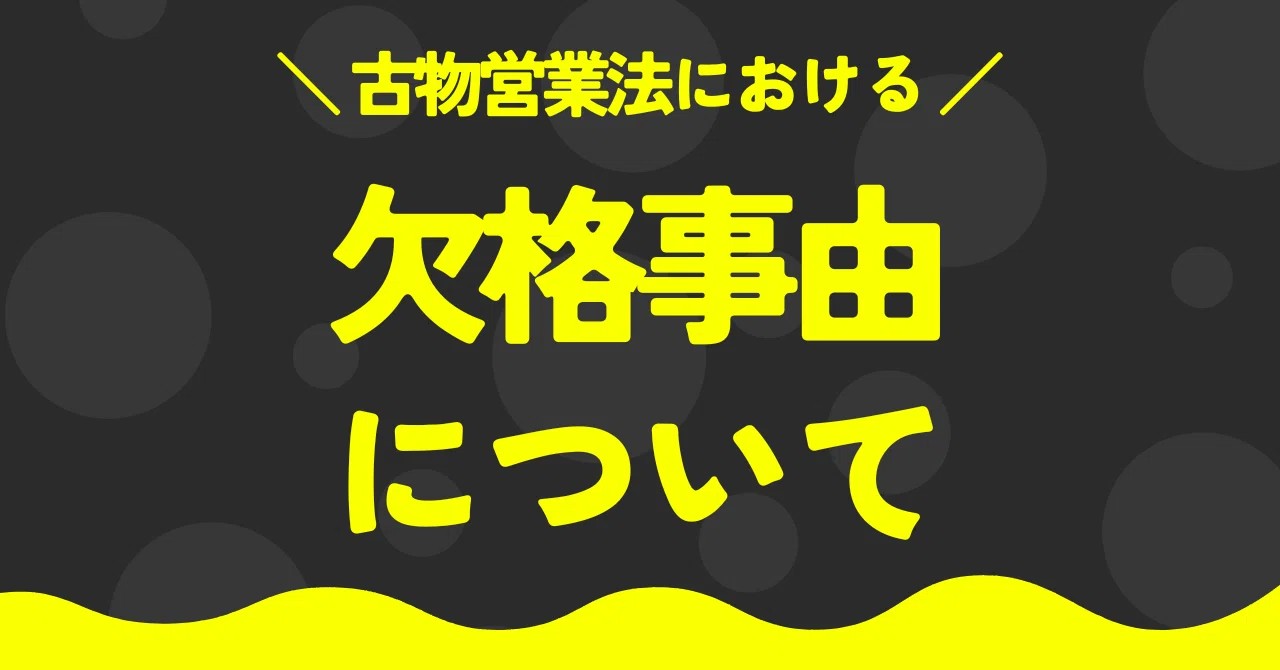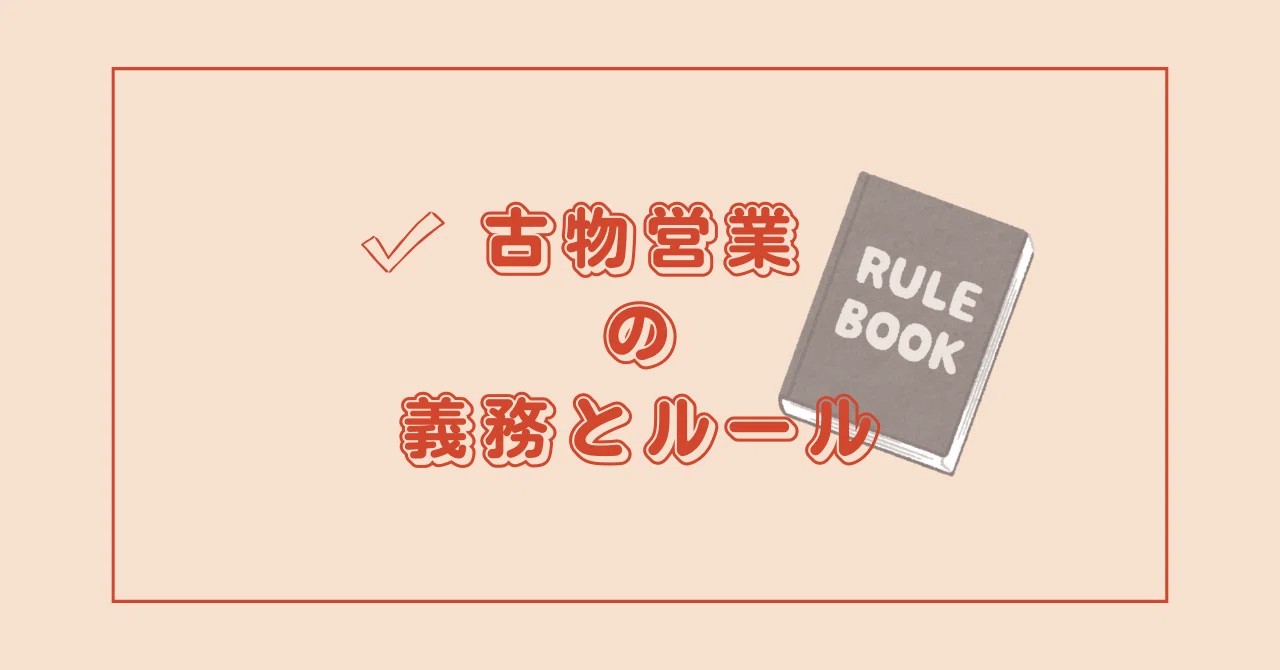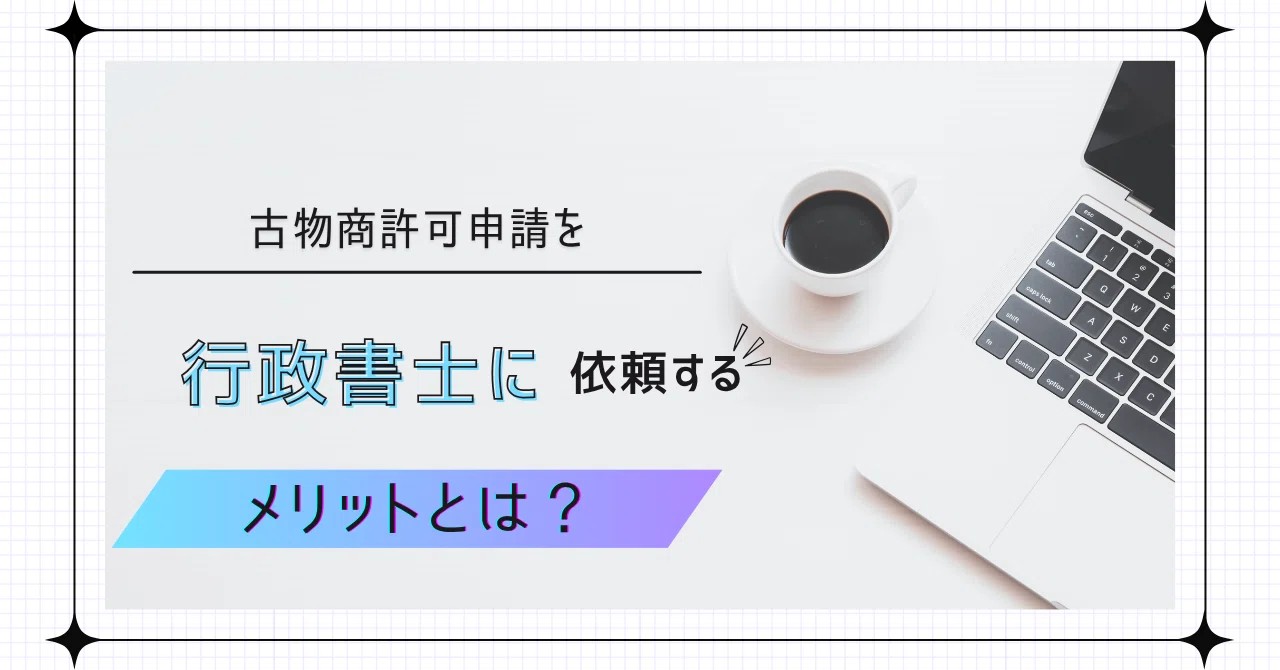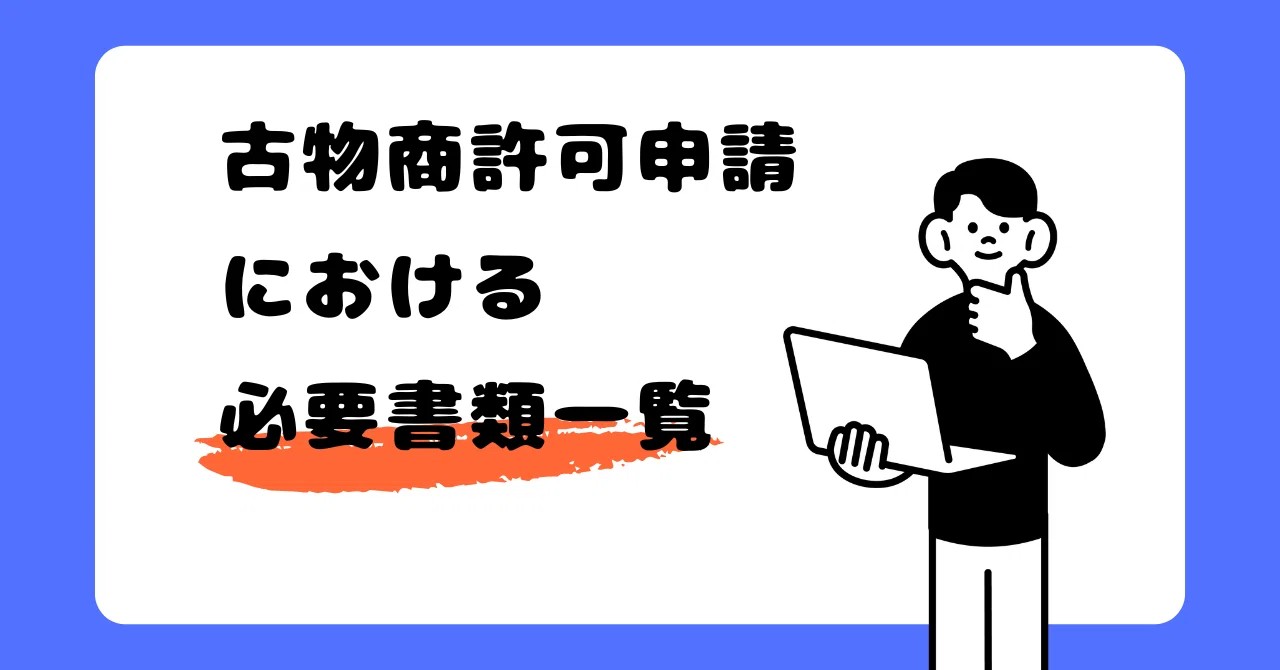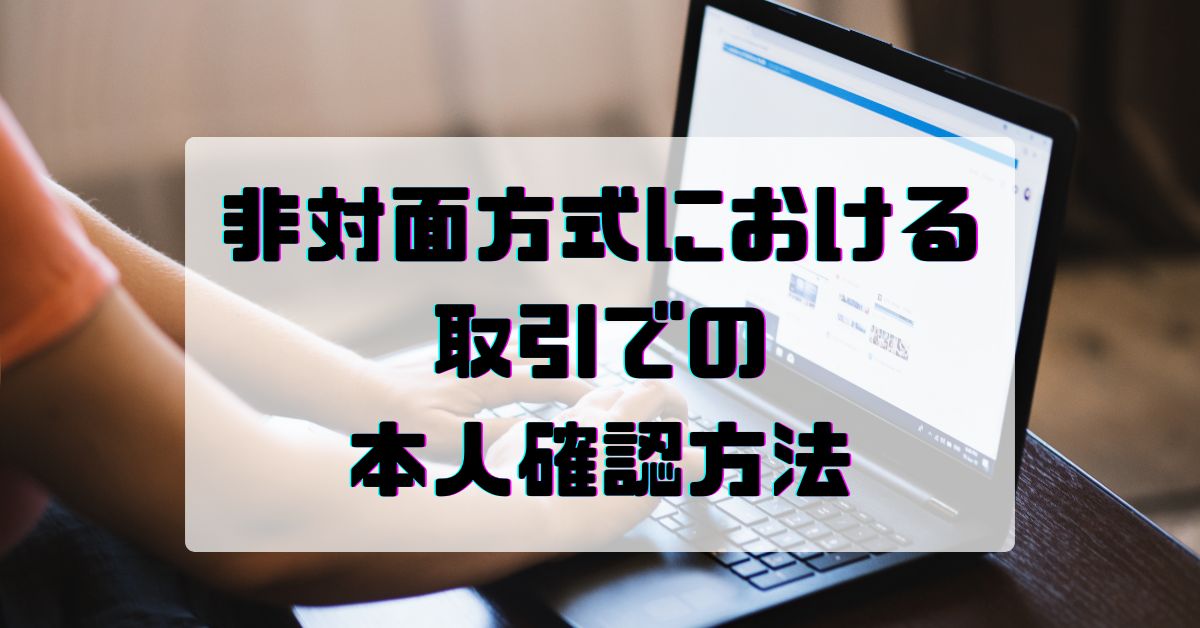これって古物商許可が必要?不要?
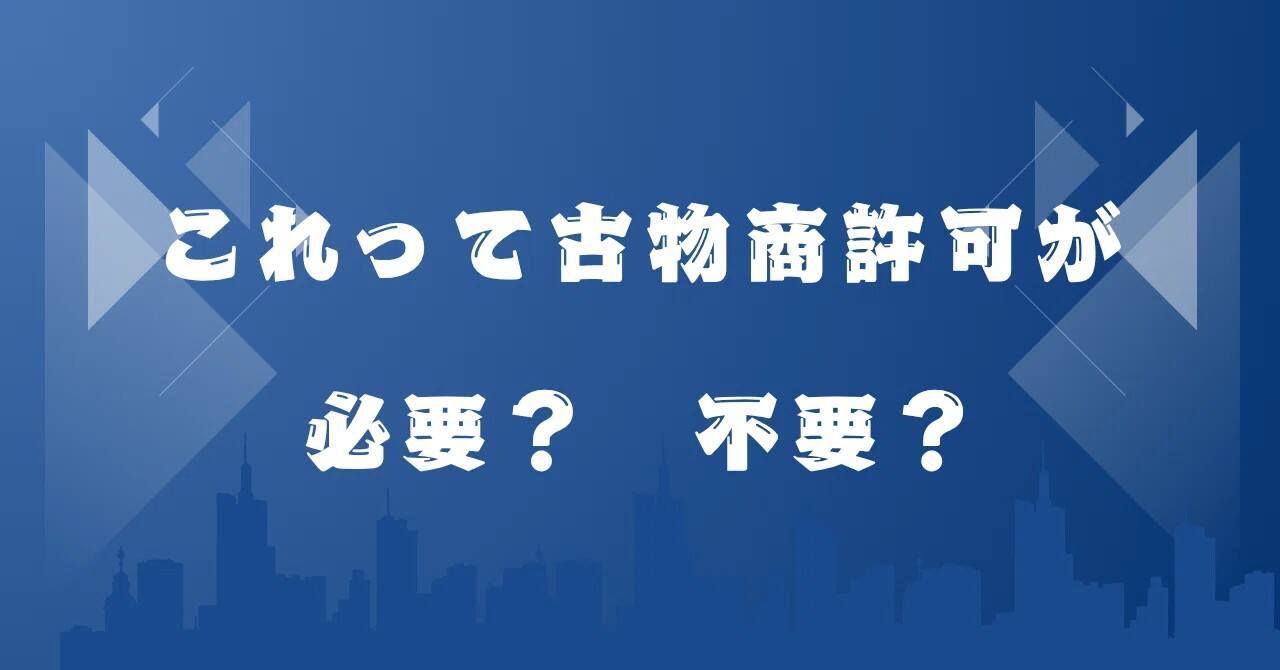
古物とは
古物を売買するためには、古物商許可が必要ですが、では『古物』とはいったい何なのでしょうか。
以下は大阪府警察ホームページより引用です。
古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。
☞ 参考 大阪府県警
すこし難しい文章です。わかりやすく言いかえると、だいたい次のような内容になります。
① 一度使用された物品
→ たとえば、中古の服やスマホなど
② 若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
→ たとえば、新品だけど個人が買ったまま使わずに売るような場合
③ これらの「物品」に幾分の手入れをしたもの
→ たとえば、中古の家具をきれいに磨いたり、直したりしたもの。物の本質を変えずに修理等を行うことをいいます。
これらの物を売買する際には古物商許可が必要となります。
古物に該当しないものとは
では、古物に該当しないものはどのようなものがあるでしょうか。
① 新品で、一度も使われていないもの(取引歴なし)
例:メーカーや小売店が仕入れたばかりの未使用品
ポイント➡まだ誰の手にも渡っていない
② 自分で作ったもの(自作品)
例:ハンドメイドのアクセサリー、手作りの家具、自作のアート作品
ポイント➡中古品に手を加えて販売する場合は許可が必要になる場合があります。
③ スクラップとして扱われるもの
例:金属スクラップなど
ポイント➡古物商許可は必要ありませんが、各自治体により金属くず商許可が必要な場合があります。
④ 個人が一時的に売る私物
例:メルカリやフリマアプリで、たまにだけ私物を売る一般人
ポイント➡反復・継続していなければ古物営業にあたりません。
⑤ 生き物や不動産
動物や不動産は古物には含まれません。
ポイント➡動物には物品として「使用する」という概念がないため、含まれません。
また、不動産は古物営業法の趣旨から離れているため、該当しません。
その他にも、古物営業法では『航空機』『船舶』『鉄道車両』『固定され容易に取り外すことのできない1トン以上の機械』など、様々なものが古物の定義から除外されています。
ここでポイントとなるのは、古物営業法の趣旨です。
古物営業法の趣旨
古物営業法第1条では、
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
このように古物営業法では盗品の流通防止という目的が定められているため、たとえば以下のような物はその目的にそぐわず、古物商の許可は必要ありません。
• 非常に大きなもの
• 非常に重たいもの
• 処分するのにお金がかかるようなもの(処分する側が費用を払うもの)
• 新品の為盗難品の恐れがないもの
これらは盗難の対象になりにくいため、法律の趣旨から外れており、古物営業の対象外とされるのです。
まとめ
上記はあくまで一例にすぎませんが、古物に該当しない物を取り扱う場合には、当然ながら古物商許可は必要ありません。
ただし、取扱う物品の種類や業態によっては、別の許認可が必要となる場合もあります。
また、自治体ごとに対応や解釈が異なることもありますので、事前の確認が大切です。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。