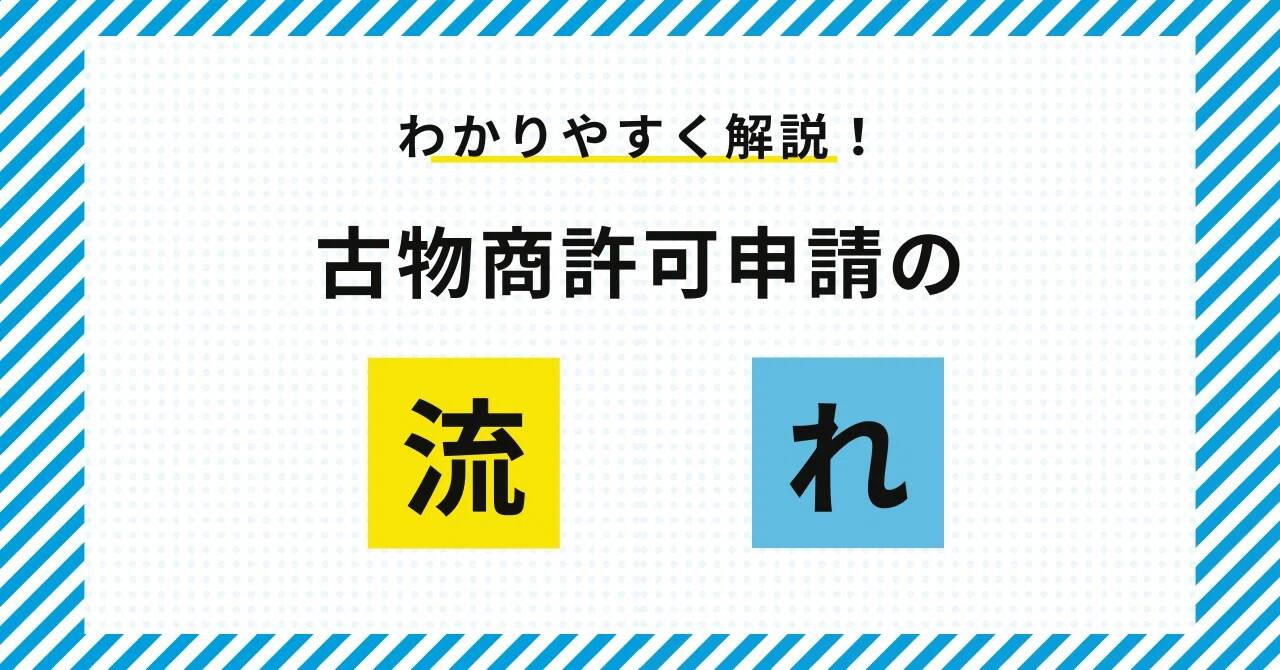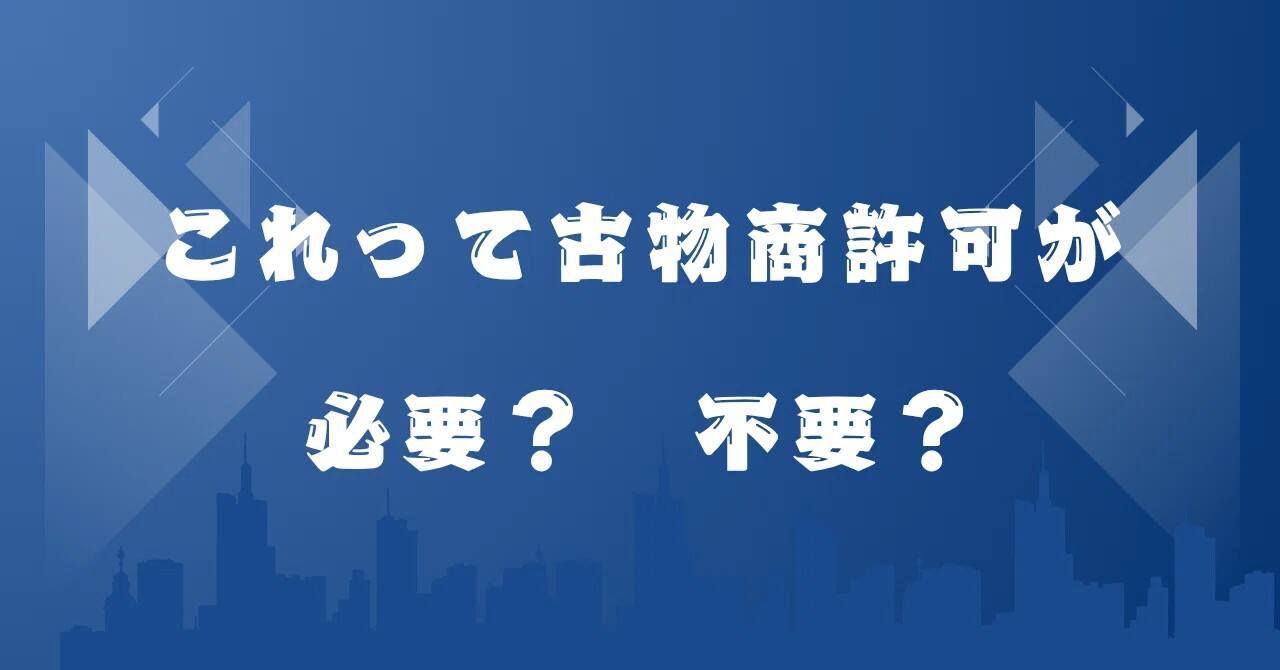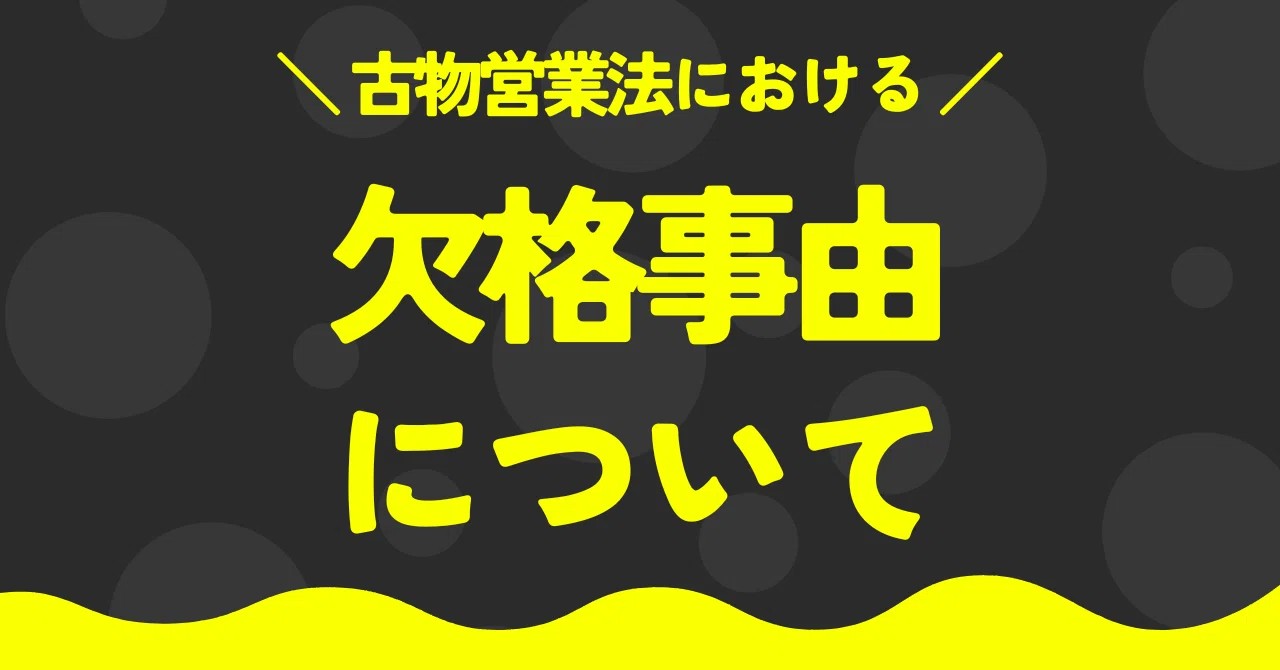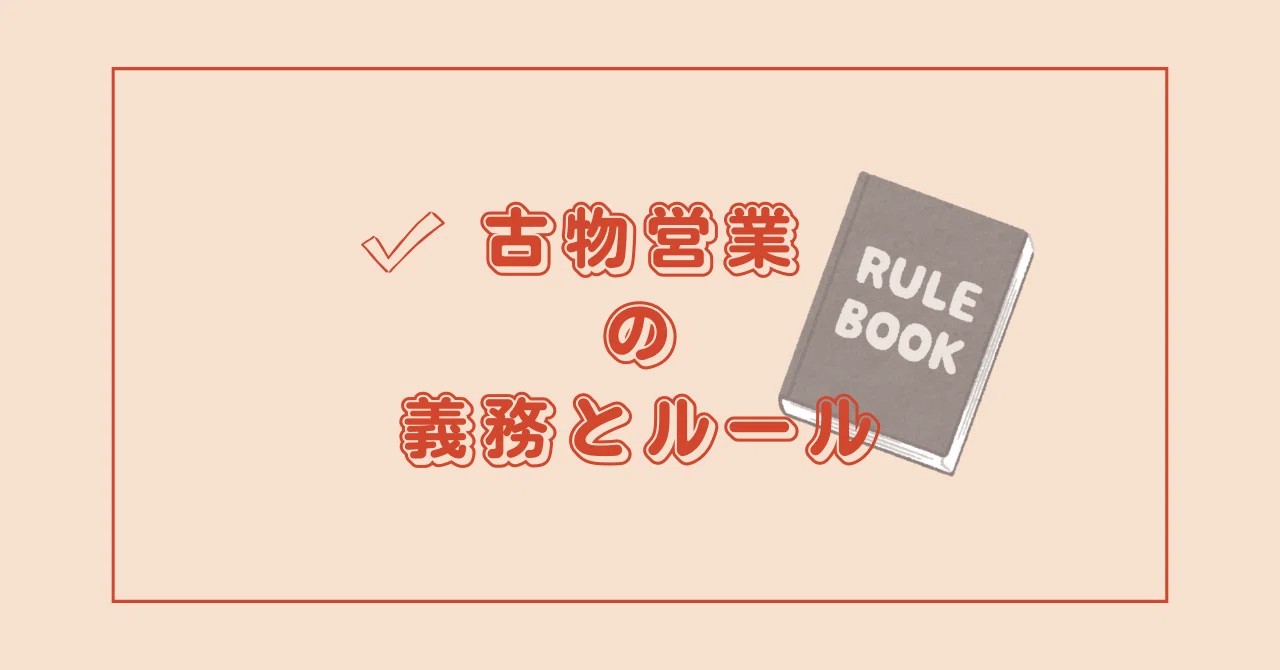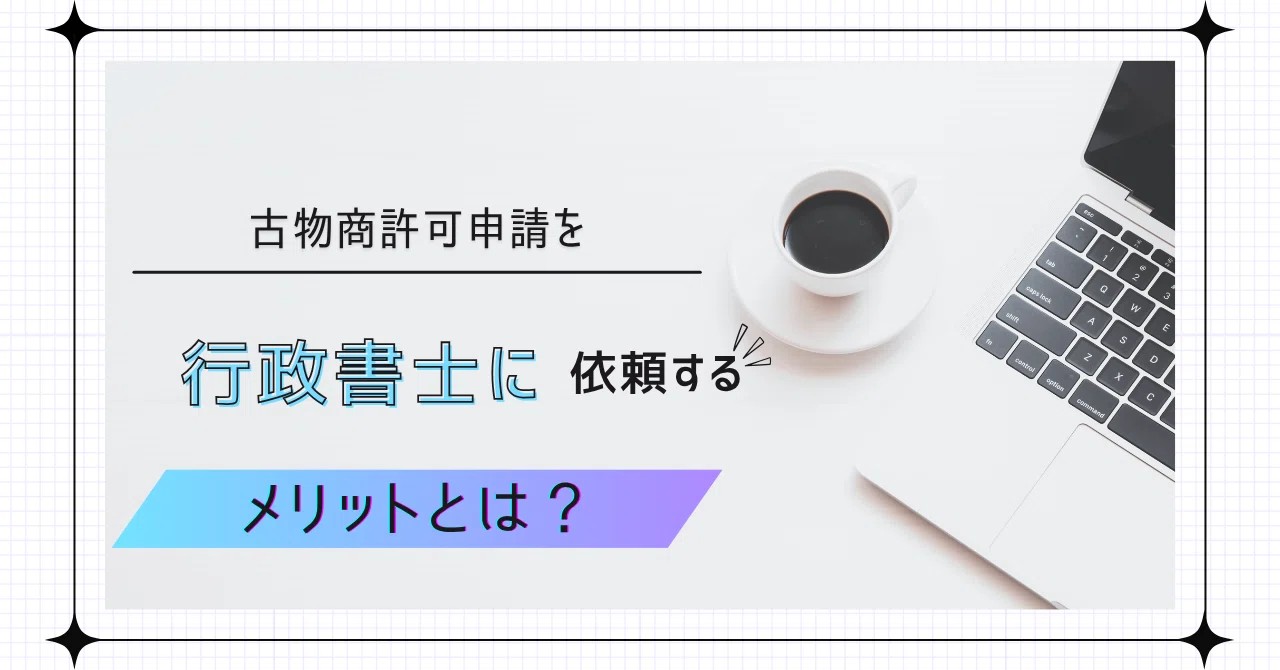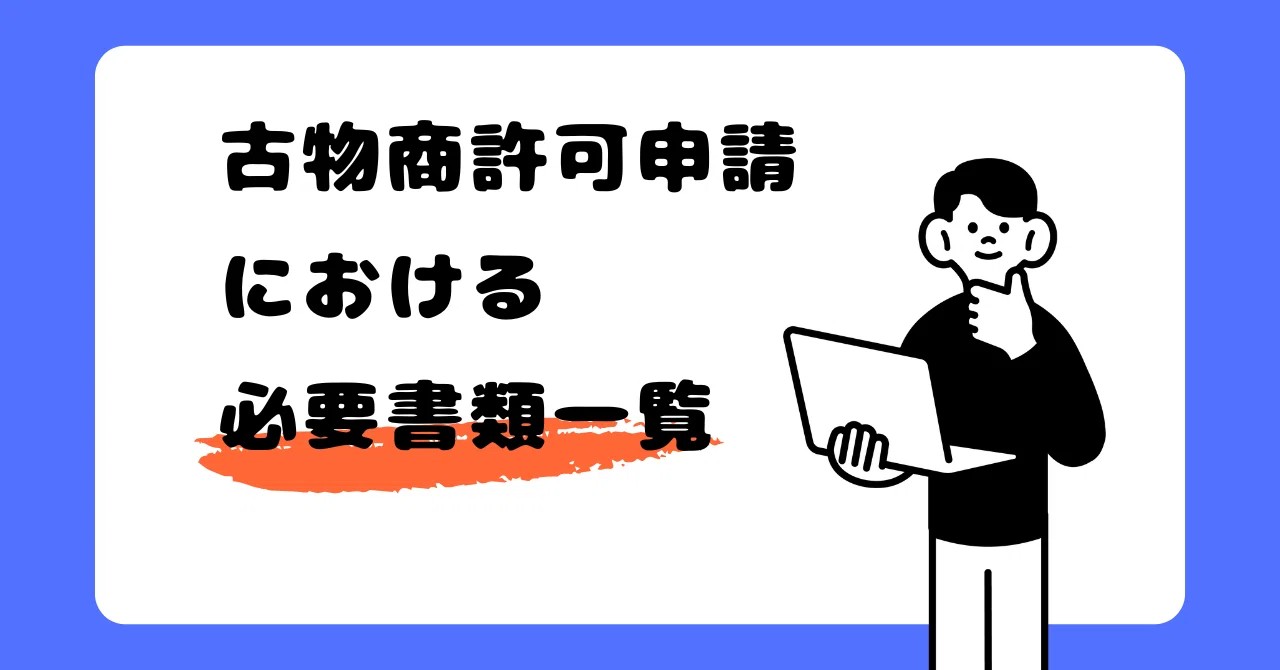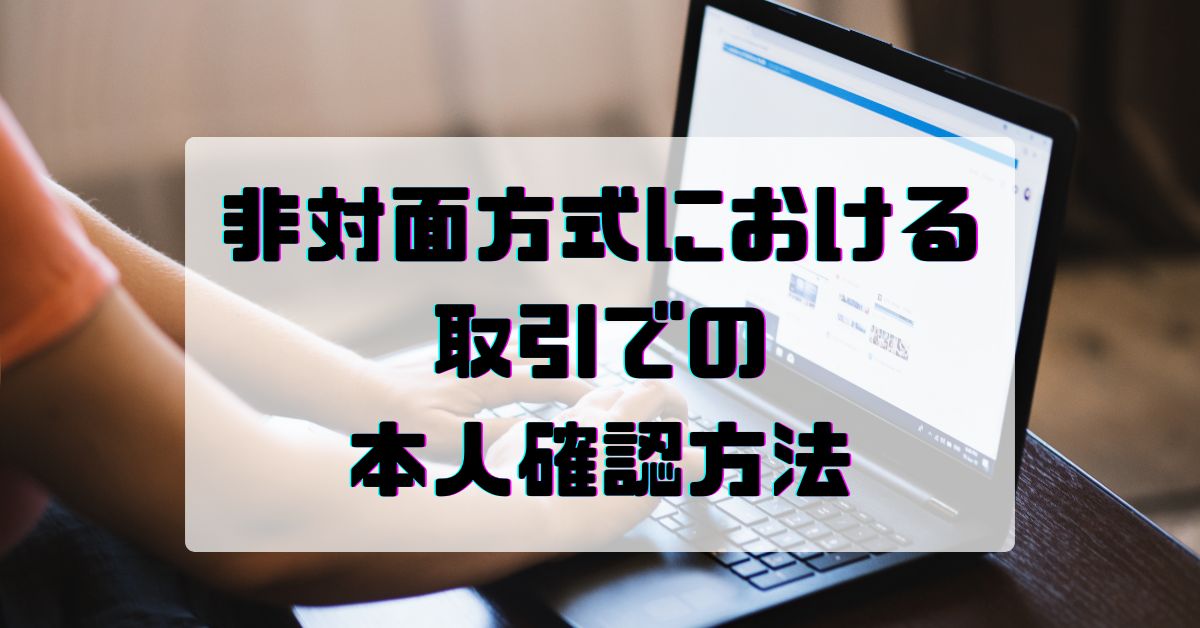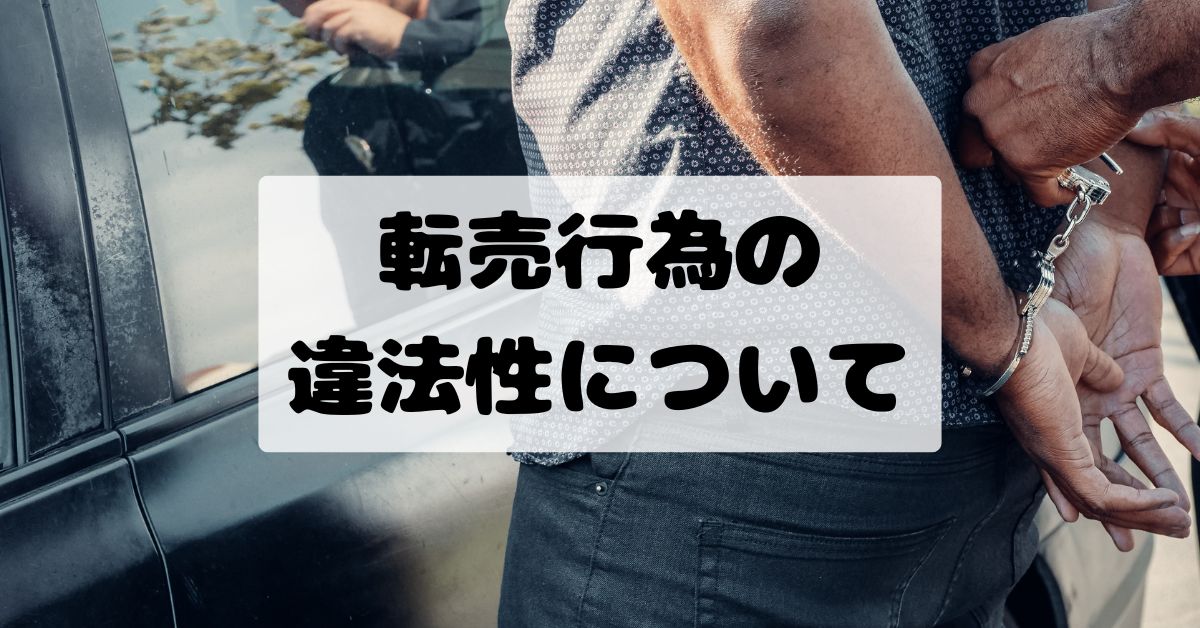本記事では、どのような場合に記載するのか。又は記載しなくてもよいのか。を解説いたします。
本記事では、どのような場合に記載するのか。又は記載しなくてもよいのか。を解説いたします。
古物台帳について

古物台帳とは
古物台帳とは、古物商が古物を買い取ったり売却したりした際に、その取引内容を記録するための帳簿です。
これは、古物営業法に基づき、盗品の流通防止や犯罪捜査に役立てることを目的として作成・保存が義務付けられた重要な帳簿です。
古物台帳の目的
① 盗品の追跡・流通防止のため
② 取引の透明性を確保するため
③ 警察などによる監査・調査への対応
帳簿等への記載義務等は古物営業法第十六条にて定められています。
この義務に違反した場合は、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科される可能性があります。
古物台帳に記録する場面
古物営業法第十六条ではこのように定められています。
『売買』『交換』『売買もしくは交換の委託』
によって古物を受け取り、又は引き渡したときは記録しなければなりません。
ただし、記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りではありません。
つまり、古物を買ったり売ったりした場合には原則として台帳への記録が義務付けられていますが、特定の取引や古物については記録が免除される場合もあります。
記録を免除された古物とは
① 1万円未満の古物を仕入(買取)する場合
ただし、以下のような盗難被害が多い品目については、1万円未満であっても記録が必要です。
・自動二輪車
・原付
・ゲームソフト
・CD、DVD
・書籍
などは盗難被害が多いため記録を免除されません。その関連製品(パーツ等)も同様です。
② 特定の古物を払い出し(売却)した場合
原則として、売却時には記録は不要です。
しかし、次のような古物を総額1万円以上で売却した場合には、帳簿への記録が必要です。
・ 美術品類
・ 時計・宝飾品類
・ 自動車、自動二輪車、原動機付自転車(パーツを含む)
未成年との取引について
記録が免除される取引であっても、未成年者との取引には十分な注意が必要です。
未成年者は契約を取り消せる場合があり、代金返還や古物の返却を求められる可能性があります。
また、自治体の条例で制限されていることもあるため、年齢確認を行うことが望まれます。
古物台帳に記載すべき主な項目
| 取引年月日 | 商品を取引した年月日 |
| 商品の名称・特徴 | ブランドや型番、状態など |
| 数量・価格 | 原則1点ずつの記載。1点の買取価格など |
| 相手の住所、職業、氏名および年齢 | 取引相手の本人確認情報 |
| 確認方法 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
古物台帳の記録方式については、法令上「記録されるべき項目が正確に記録されていれば、手書きでもパソコン(電子データ)でも問題ない」とされています。
古物台帳の保管期限について
古物営業法第18条では、古物台帳(帳簿)の保存について次のように定められています。
① 最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付けておかなければなりません。
② 電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておく必要があります。
この規定は、警察による監査や照会に迅速に対応できるようにするためのものです。
まとめ
古物台帳は、盗品の流通防止や取引の透明性を確保するために、古物営業法で厳格に定められた帳簿です。
取引内容を正確に記録・保存することは、古物商としての信頼を守るうえで非常に重要です。
ルールはやや複雑に感じられますが、近年では、インターネット上で古物台帳のひな型や記録用アプリを無料で入手できるようになっています。
こうしたツールを上手に活用しながら、法令を遵守しつつ安心・安全な古物取引を行うことが大切です。
適切な記録管理を心がけ、健全で楽しい「古物ライフ」をお過ごしください。