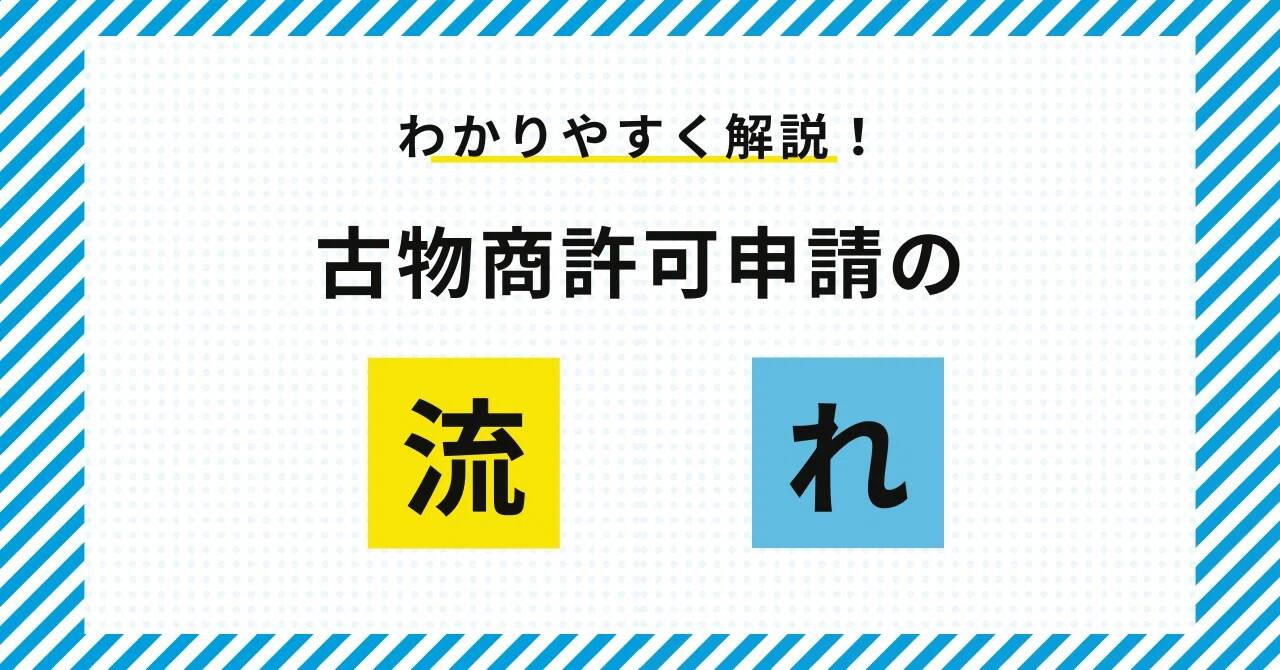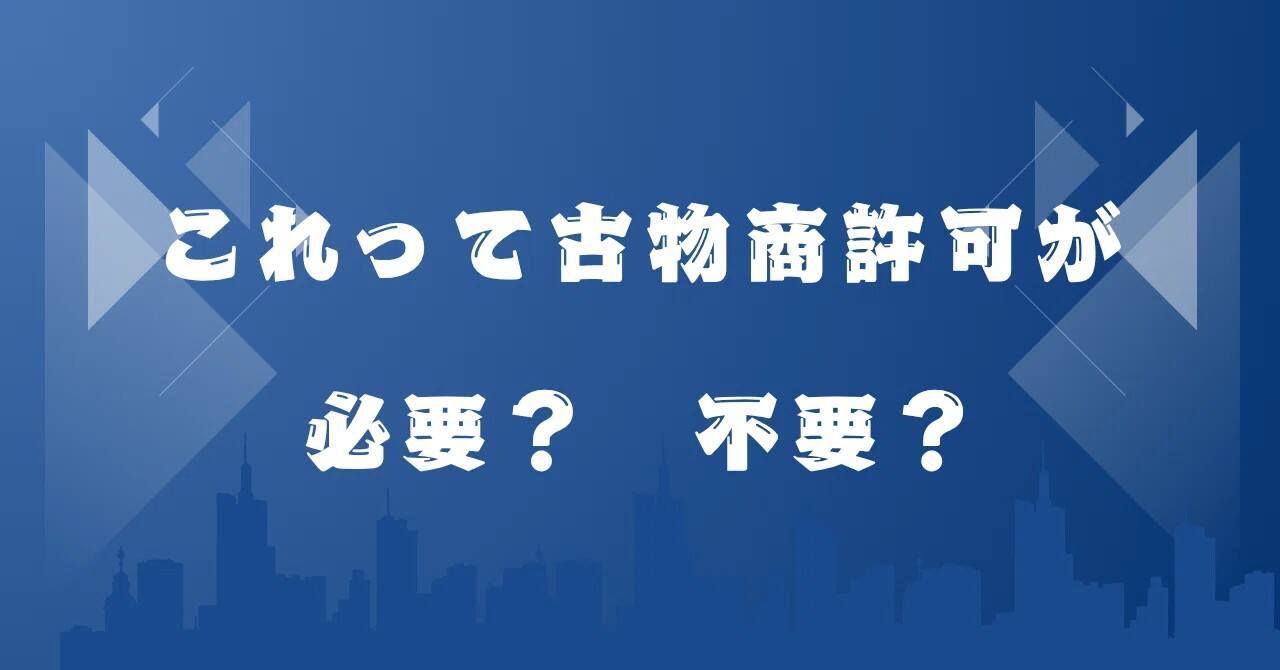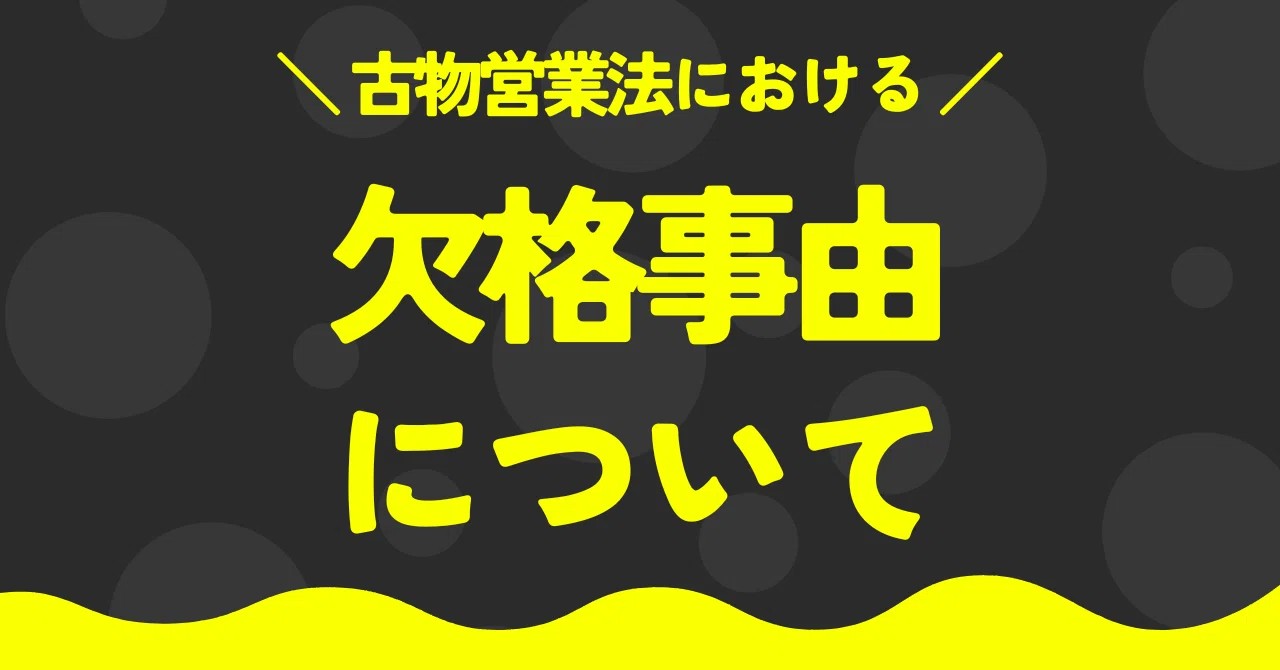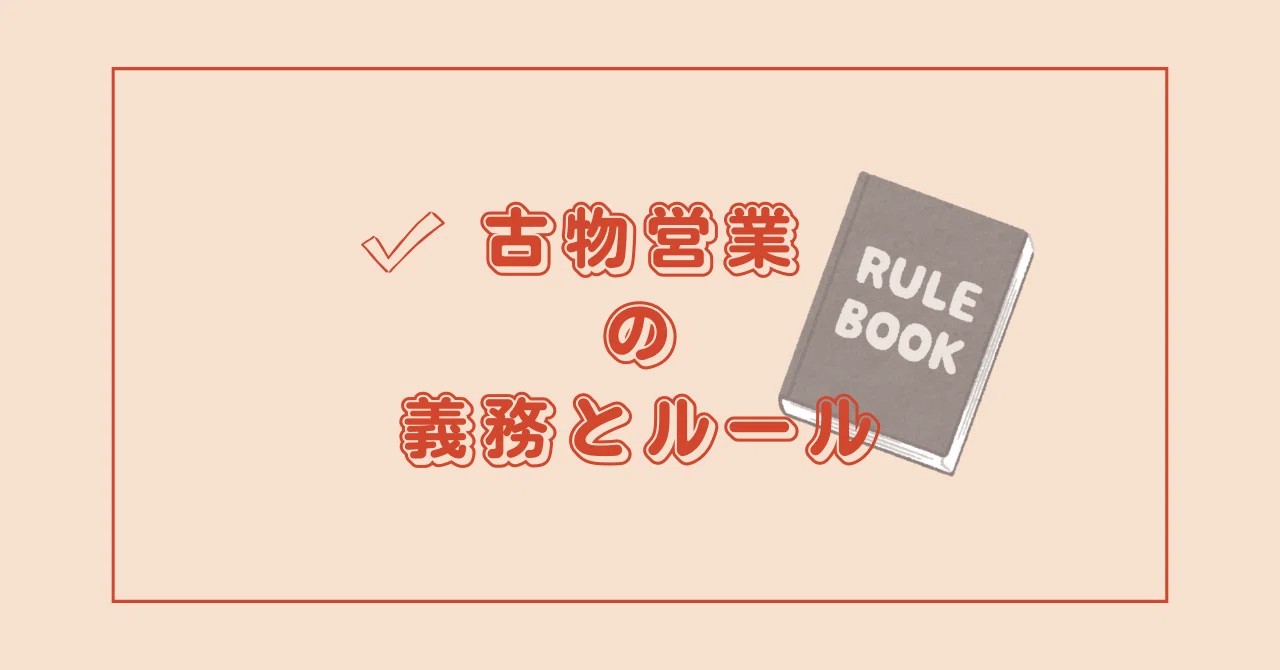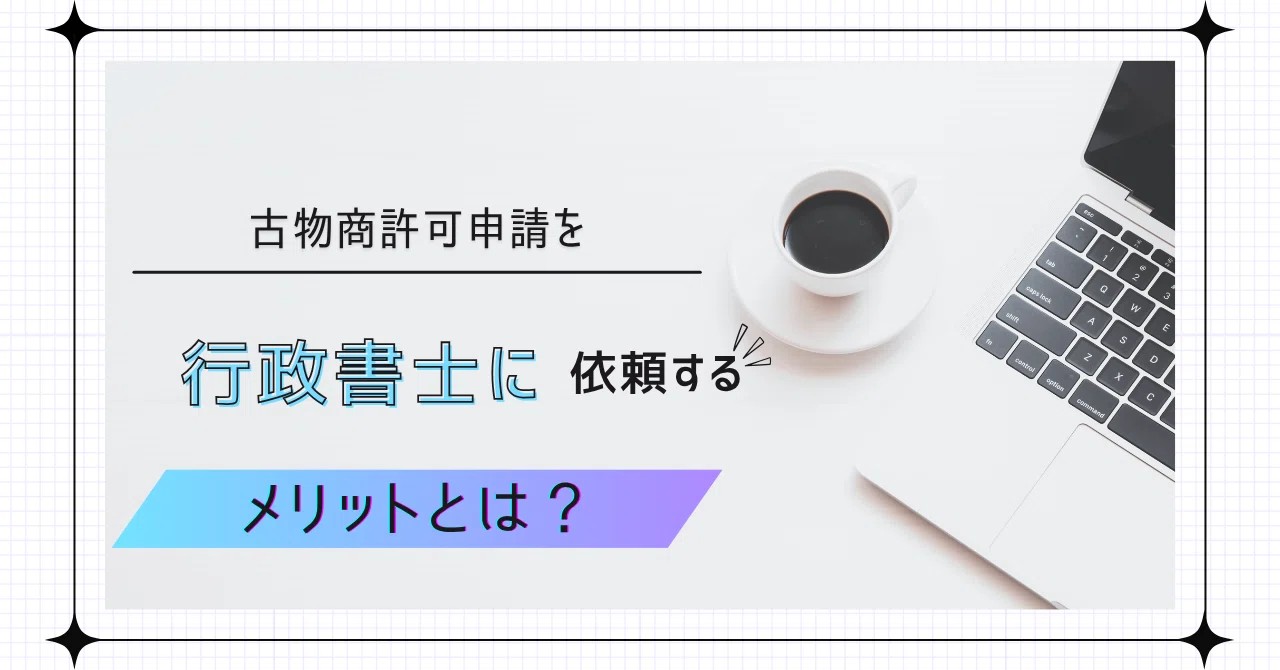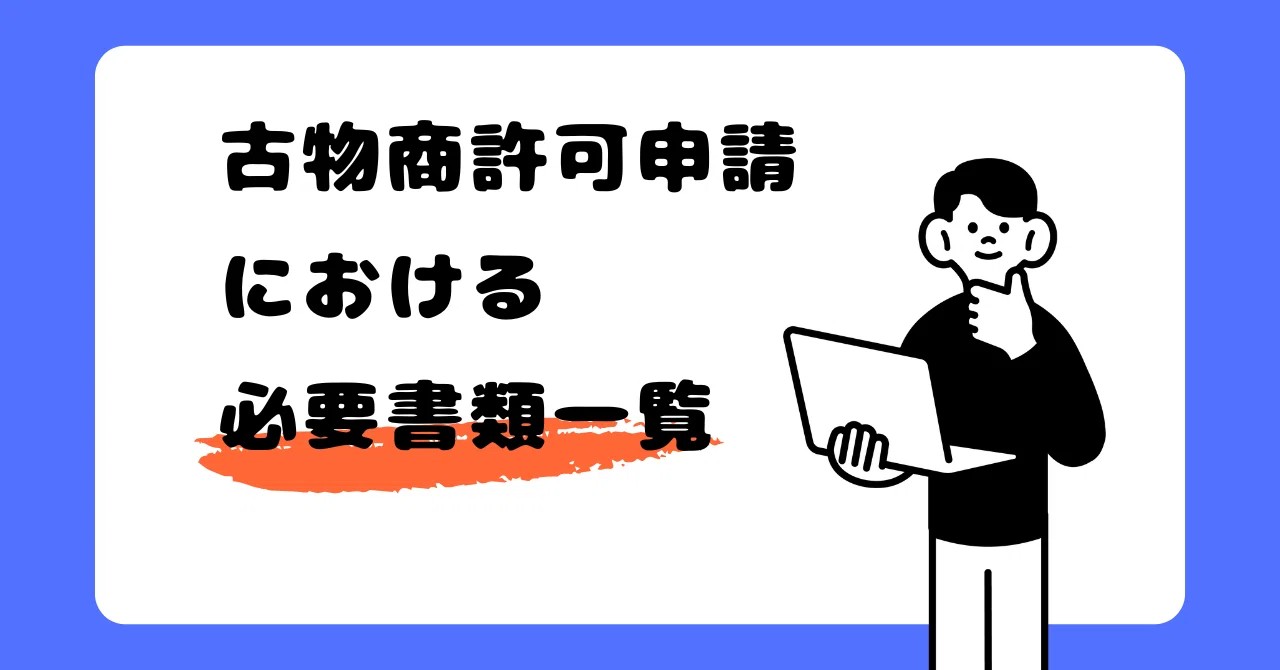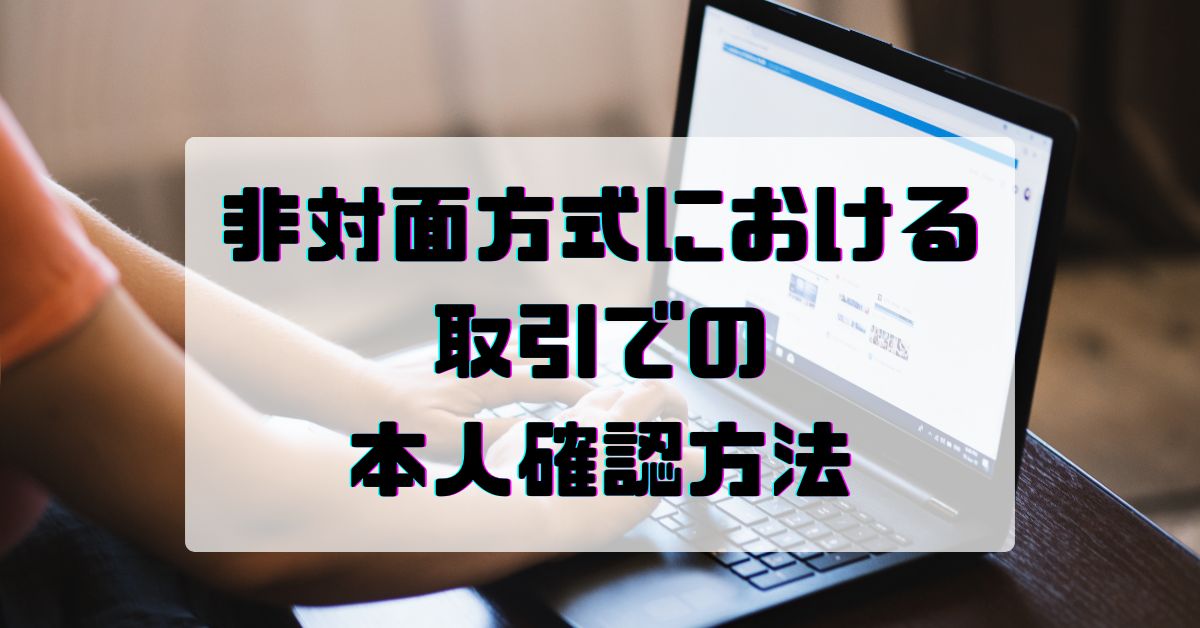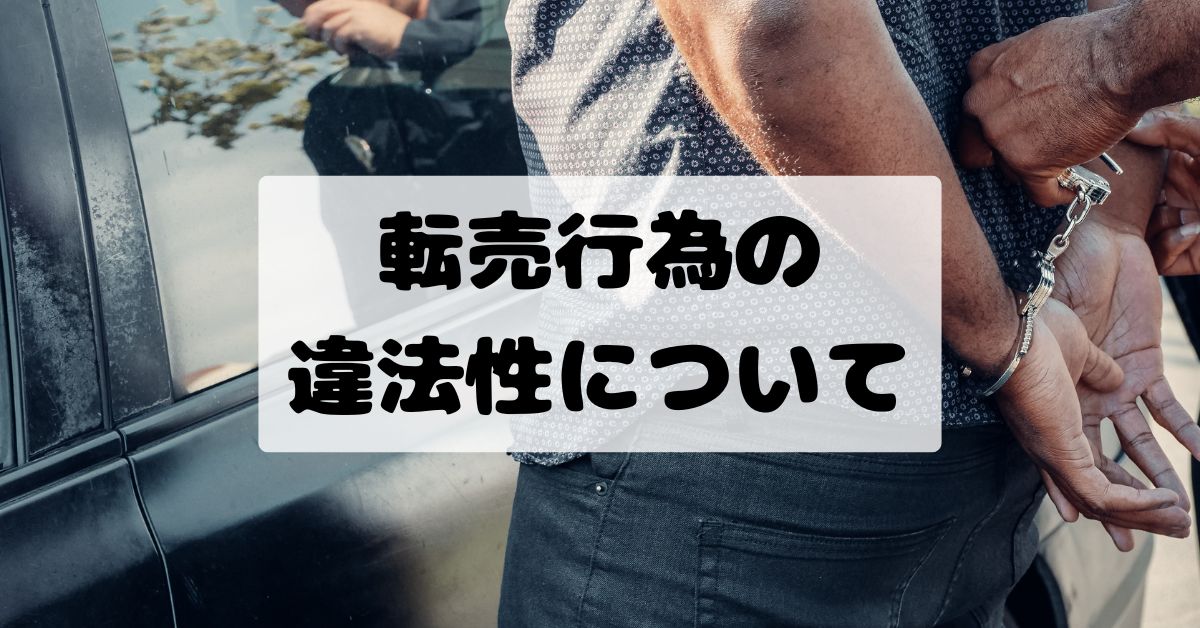未成年からの買取について

未成年との古物取引について
リサイクルショップやネット買取サービスなど、古物を取り扱う場面は年々増加しています。
その中で、「未成年者が古物を売却できるのか?」という問題は、古物商にとって非常に重要なテーマです。
本記事では、法律的な観点と実務上の注意点を整理して解説します。
未成年の売却は法律上認められているのか
果たして、未成年から買い取ることは法的に可能なのでしょうか。
ここでは、『民法』『古物営業法』『青少年育成条例』の3点からその可否について解説したいと思います。
民法上の決まり
民法では、未成年は法定代理人(多くの場合、親権者)の同意なしに契約を締結した場合、その法定代理人または未成年者本人が、その契約を取り消すことができます。
契約を取り消すと、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。
その結果、以下のような取り扱いになります。
・未成年者は、代金支払などの義務を履行する必要がなくなります。
・未成年者が、すでに支払った金銭や引き渡した商品があれば、返還を請求できます。
・未成年者が受け取った商品やサービスは、「現に利益を受けている限度」で返還すれば足りるとされています。
このように、契約そのものは可能ですが、親の同意がないまま契約を行うと、後日取り消されるリスクがある点には十分な注意が必要です。
古物営業法上の決まり
古物営業法では、未成年者との売買契約を禁止する規定はありません。
つまり、法律上は未成年者と古物の売買契約を結ぶこと自体に違法性はなく、理論的には可能とされています。
しかし、実際の取引においては、未成年者であることを把握していたにもかかわらず、親権者の同意なしに高額品を買い取るような行為は、民法上の取消リスクを高めることになります。
そのため、古物商としては、身分証明書による年齢確認を徹底し、必要に応じて親権者の同意書の提出を求めるなどの対応が求められます。
青少年育成条例の決まり
「青少年育成条例」は、各地方自治体ごとに定められている条例で、名称も地域によって異なります。たとえば「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」といった呼称が使われています。
たとえば、埼玉県の『埼玉県青少年健全育成条例』では、古物商による未成年者(青少年)との取引について、次のように定められています。
古物商は、古物を青少年から買い 受け、青少年を相手として交換し、又は青少年から古物の売買若しくは交換の委託を受けてはならない。
ただし、当該青少年が親権を行う者又は後見人の同意を得たと認められるときは、 適用しない。
このように、条例では未成年者との古物取引自体を禁止している場合があり、親権者や後見人の同意がある場合にのみ例外的に認められるケースもあります。
ただし、具体的な規制内容や適用年齢は自治体ごとに異なるため、事業者としては営業する地域の条例を必ず確認することが重要です。
気になる場合は、取引対象地域の地方公共団体の公式サイトで該当の青少年健全育成条例を確認するようにしましょう。
親権者や後見人の同意を得る手順
では、未成年者と契約を結ぶ際、どのような場合に「親権者等の同意を得た」とみなされるのでしょうか。
一般的には、以下のような対応があれば、同意があったと判断されるケースが多いとされています。
・保護者が取引に同伴している場合
・保護者の同意書を未成年者が持参している場合
・その場で電話連絡を取り、保護者本人から同意を確認した場合
これらの方法は、いずれも「親権者等の意思を確認した」という証拠として残すことができます。
トラブルを未然に防ぐためにも、古物商としては必ずいずれかの方法で親の同意の有無を確認・記録しておくことが重要です。
まとめ
未成年者が古物を売却すること自体は、法律上は可能です。
しかし、民法上では、親権者の同意がない契約は後に取り消される可能性があります。
さらに、青少年育成条例により、自治体によっては未成年者との取引が制限されている場合もあります。
このような契約の取り消しや条例違反のリスクを回避するためには、古物商として本人確認を徹底し、未成年者であることが判明した場合には、親権者の同意書の提出や同伴などにより、確実に同意を得たことを確認することが不可欠です。